- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
木靴の樹 1978伊 エルマンノ・オルミ
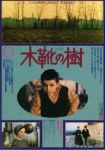
19世紀後半の北イタリアの小作農の生活を、
タイムスリップして覗き見たような映画です。
脚本も演出もなく、
貧しい4家族が生活している姿を切り取ったドキュメンタリーのような映像が流されます。
その世界は当時の農業そのものを再現しています。
今ほど収穫が約束されていない農業と、
牛と馬とあとは人手でなにもかも行う重労働、
あまりにもリアルな鳥や豚の解体、
そのどれもが演技でも演出でもなく自然の振る舞いです。
冒頭から一時間あまりは、そんな一年間の生きるための農作業を中心に、
祈りの生活の様子や子供の成長による変化、
新しい命の誕生による変化を挿入します。
家畜と人力による前時代の過酷だった農業の現実は、
家族と隣人とが力を合わせてやっと食いつなぐ糧を手にできるというものです。
そこは封建世界末期で、
生かさず殺さずから逃れられない社会の仕組みに組み込まれた農民の姿です。
働けど働けど2/3の徴税の元では、ろくな貯えなどできません。
でも、そんな苦しい毎日の中でも時折、楽しい出来事=喜びがあります。
後半からはそんな非日常も見せてくれます。
(たぶん)一年に一度のお祭り、そこでは食べ放題、飲み放題です。
それ以外に、時折訪れる商人の姿もあります。
商人も、農民たちには待ちわびた存在です。
パリからのハイカラな衣装を積んだその荷は、彼らにとっては垂涎の的です。
けれど、奢った見方ですが、祭りも商人の登場も、
爪に火を点した貯えすらも奪う行事と見えてしまいます。
たとえそうであっても彼らの精神の拠り所です。信仰と共に。
他にもちょっとしたエピソードを見せます。
金貨を拾い夢心地になる農夫、それを無くしてしまうところが彼らしく、閉塞を見ます。
工夫を重ねた新しい技術の農作業で、他の家族を少しでも出し抜きたい姿、
地主から借りている牛が病気(その家族の死活問題)になり、祈りで復活するシーン、
孝行息子が遠い道のりで学校に通う中で
木靴が壊れるエピソード(これが結末につながります)、
4家族の中の一家族の年頃の娘と村の青年との結婚、
そして新婚夫婦がミラノ(都会)にいくシークエンス、そしてそれは、
生活に糧のために養子を貰い受けるという現実。
後半もゆったりした流れは変わりませんが、
年月が経つことで人が行う慣習を映します。
ミラノのくだりでは、これから崩れていく封建時代の予兆が窺えます。
そして、木靴のための樹を切り落とした農家に罰則を科せられるラストに入り、
この物語は終わります。
絶望を宣告されたこの一家族は、一頭の馬にささやかな家財道具を乗せて、
行くあてなく彷徨いの途につきます。
ほとんどの映画の方程式から離れた、ただただ一時代を再現した映像に、
観客は己に潜む感覚を重ねてこの物語を感じ取ります。
そこには農民たちと一緒になって人が生きる苦を体感します。
苦の中の喜びを重ねようとします。
あまりにも不条理に怒りを持つというよりも
受け入れなければならない現実を受け止めようとします。
絶望に落とされた一家族の姿でこの映画が終わることが告げられます。
そこで改めて、彼らはどうするのかと、映画の世界と離れてそれを気にかけます。
その後、この家族はどうしようもないということを悟ります。
そして、これらがこの時代の未来=現在を造ったのだと感じます。
この映画も、抱えきれない、答えを出し切れない主題を私に投げかけました。

