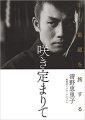いもたつLife
咲き定まりて 市川雷蔵を旅する 清野恵理子(著)
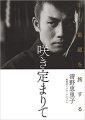
映画を観ていると、男優でも女優でも、「この人は不世出だ」という人に出合います。
その素晴らしい面々の中でも、個人的に日本の男優のno.1だと確信しているのが市川雷蔵で、もうこの人を超える人は出て来ないだろうとまで思っています。
この本で紹介されている映画で観ているものの中で、印象に残っている映画の章では、大きく頷いたり、涙が溢れてきたりしました。
そして、あれだけの演者だった市川雷蔵を今まで以上に知ることもできました。
著者はじめ多くの人に愛されていることもより感じ、題名通り“市川雷蔵を旅する”ことができました。
著者に感謝申し上げます。
【いもたつLife】
メアリー・エインズワース 浮世絵コレクション

展示点数も多く、内容も充実している展覧会でした。
浮世絵の技術進歩や当時の流行りを時系列で追えるので、その歴史も知る事ができ、一人の作家の複数展示により個性を窺うこともできます。(写楽だけは活動期間が10ヶ月だったからか、1点のみでした)
良く知られている風景画は、浮世絵の歴史のなかでは本当に後期だったことも知りました。
その風景画も、北斎の作品は一芸術家という印象から、国芳になると映像作家という印象になり、広重になると、チームで映画を作っているように感じます。
小津安二郎のカットや溝口健二の長回しを想像させます。
見応えあり、見どころたくさんでした。
【いもたつLife】
第18回 柳家家禄 独演会

恒例の静岡江崎ホールでの独演会です。
毎回家禄師匠のお弟子さんが一人お付で、一席披露されますが、これも楽しみにしています。
今年は10人いる中の三番弟子の緑君さんでした。演目は「祇園祭」で、枕からの引き込みも含めてとても上手。真打が近い二つ目さんでした。
師匠の一席目は「粗忽の使者」。師匠の師匠の小さんの「粗忽の使者」もよく音で聞きますが、ひけをとらない出来です。以前やはりとても好きな小さんの「猫の災難」の家禄師匠版を聞いた時も同じ印象でした。
仲入り後は「子別れ」です。たっぷり、一時間近くも熱演でした。
もちろんどちらの枕も面白く、今回も堪能しました。
【いもたつLife】
【spac演劇】イナバとナホバの白兎 演出:宮城聰

この作品は、フランス国立ケ・ブランリー美術館の開館10周年の記念公演のために、SPACに創作依頼されて出来たものです。2016年に駿府城公園の野外劇場でお披露目があり、その後パリのフランス国立ケ・ブランリー美術館クロード・レヴィ=ストロース劇場で上演されまました。
創作のきっかけは、レヴィ=ストロースの最後の著作「月の裏側」に出てくる仮説です。
イナバの白兎を含めた日本の神話と、アメリカ先住民ナバホ族の神話とは、所々似ている、それは、アジアのどこかでその元になる神話があり、日本に伝わり、その後北米に伝わったのではないか?今はまだその元の神話は発見されてはいないが。
ということが発端で、ならば、日本の神話とナバホ族の神話から、逆にその元になる神話を想像して創造してみようというのがこの「イナバとナホバの白兎」です。
今年はレヴィ=ストロース没後10年ということで、もう一度クロード・レヴィ=ストロース劇場で再演となり、そのためにもう一度練り直されて今度は屋外ではなく、屋内の場謡芸術劇場で、パリ凱旋に先駆けての上演でした。
2016年よりも迫力が増しているのが印象的でした。屋外よりも近いために臨場感もあります。
3部構成で、「イナバの白兎」「ナバホの神話」そして「想像創造の物語」に入るのですが、細工は流々仕上げを御覧じろとばかりに、第3部の大団円は場内が一体になります。
人類が誕生し、狩猟を覚え、農耕を知り、争いもあり、神(太陽)を畏敬し、辿りついたのは、神に感謝することと、一人では生きていけないことの深い認識であることを謳い上げている壮大さを感じました。
そんな人の営みは貴くて、それを祝う祝祭の劇です。
素晴らしかったです。
【いもたつLife】
ギュスターヴ・モロー展

良かったです。
目玉の「出現」「デリラ」「セイレーン」「パルクと死の天使」「一角獣」等々ももちろんですが、習作が多く展示されていて立体的に感じます。
また、ギュスターヴ・モローの人となりに触れることができるプログラムでした。
パリのギュスターヴ・モロー美術館に行きたくなりました。
追伸
6/6は「芒種」です。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「芒種」の直接ページはこちら
芒種
【いもたつLife】
【SPAC演劇】マダム・ボルジア 演出:宮城聰

spacの新作「マダム・ボルジア」は稀代の悪女ルクレツィア・ボルジアが自分が犯してきた数々の大罪から、実の息子ジェンアロに母親を名乗れず、しかもジェンナロを傷つけてしまっていることに苦悩する物語です。
多くの暗殺に絡み、政略結婚で闇の政治にも関わり、ボルジア家の一員らしく残虐でもあったらしいのですが、この「マダム・ボルジア」のルクレツィアを演じている女優の美加理は、絶世の美女で高貴であったルクレツィアらしさは十二分ですが、残酷な悪女のイメージはありません。
駿府城公園に特設された野外会場に響く透き通る声やその優雅な立ち居振る舞いで、ジェンナロを愛する姿はただ一人の息子を想う母であり、恋人を慕う一人の女です。
多分そういった面は、歴史を踏まえた上でのこの戯曲のルクレツィアらしいのは間違いないですが、それでも美加理はあまりにも一途で到底稀代の悪女には重なりません。
この「マダム・ボルジア」は当然それを踏まえて造られています。
それは何故か?
「マダム・ボルジア」は3回観劇しました。その3回目はそれを考えました。
ひとつ思いついたことがあります。それは人は不可解ということです。
こんな高貴な方が、ボルジア家のためとはいえ、いとも簡単に多くの人を毒殺するわけがない、ということはない。ということです。
そして、多くの者たちから憎まれる女であっても、愛する者を自分の命よりも大事に想うのは当然であるということです。
当たり前の結論になってしまいますが、今の自分は自分が決めた自分である部分はとても少なく、でもそれを踏まえて生きていることを自覚しなければならない(大変ですが)ということです。
環境で造られた要素は大きく、立場と役割があります。今の造られた自分は理不尽であったと嘆くこともあるでしょう。でもそれをひっくるめて自分であり、ではどう生きるかでしょ。と、説いているのが「マダム・ボルジア」で、だからルクレツィアを美加里が演じたのではないかと推測しました。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】歓喜の詩 演出:ピッボ・デルボーノ

演出家で出演者のピッボ・デルボーノさんと20年以上一緒に舞台を造ってきたボボーさんに捧げる演劇ということです。
そして冒頭、歓喜に至るまでの劇とナレーションが入りはじまりました。
抽象的なイメージで進みます。
劇全体を通して華が重要な小道具であり大道具です。
真っ暗闇の中、一輪の花が増えていくことから始まり、劇の終盤では誕生した赤ん坊は花に囲まれ、そして舞台は花一色にもなります。
また舞台は、ピエロのような衣装を纏った俳優たちが狂うように踊ったり、舞台で進行役と努めるピッボ・デルボーノさんが、檻に囚われたり、叫び声をあげます。
精霊流しのような無数の紙の船が並ぶ場面もあります。
そして、散漫に登場していた俳優達が最後に向かい近づきます。
この劇はやはり喜びを表現して終わっていることが感じられます。
アフタートークを聞くと、大事な仲間と造った演劇だったと解ります。
ピッボ・デルボーノさんと俳優達がこの世で出合った仲間と、喜びを、とても過激に、でも真摯に表現していた劇であると解りました。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】マダム・ボルジア 演出:宮城聰

spacの新作「マダム・ボルジア」の原作はヴィクトル・ユゴー「ルクレツィア・ボルジア」で、ボルジア家が隆盛だった頃、スペインが世界の覇者として馳せてた時代の話で、時間軸はそのままに、日本の戦国時代に空間を移しています。
ルクレツィアの父は関白、兄チェーザレも4番目の夫アルフォンゾの将軍という設定です。
ルクレツィアが愛してやまないジェンナロは傭兵の勇敢な隊長という設定は原作と同じ、そして、彼と共に戦場を駆け抜けてきた、一緒に死を共にすることを誓い合った無二の親友達は、日本各地の領主の若頭という設定です。
その日本各地から集まってきたという設定を活かしています。
この劇は二部構成で、ルクレツィアにとってビハインドの水の都(ここでルクレツィアは辱められ、後半の復讐に繋がります)から、ルクレツィアのホーム(夫アルフォンゾの領地)の高峰の都に、舞台自体も観客も移動するのですが、観客は五つの国の若頭に先導されて移動します。
その若頭の領地は、それぞれの俳優の出身地で、俳優達は方言を使います。また、宴の場面が一部でも二部でもあるのですが、そこでもそれを匂わせます。特に一人の若頭は地元静岡の遠江出身で、静岡弁が飛び交います。
この「マダム・ボルジア」はボルジア家のダークないわれが下敷きになっているので、圧制、残虐、毒殺、近親相姦等がボルジア家にはあり、とてもきな臭い上で話は進むのですが祭りの場面では明るく、でも人が集まらない場面では本音が出る演出をしています。
明るい宴とは裏腹に、ルクレツィアが部下のグベッタと二人の時、アルフォンゾと部下の捨助と二人の時の、彼らのダークな企てをする場面の暗黒との対比が強調されます。
また、ルクレツィアとアルフォンゾの二人の腹の探り合いは二人の愛は程遠く、政略結婚であることが案じられます。
それとは全く違う雰囲気がルクレツィアとジェンナロの二入の場面で、ルクレツィアの彼に対してだけ注ぐ純粋の愛は、政治や経済や面子を抜きにしたもの、でも、ジェンナロはその勇ましさもあり、ボルジア家の暗黒に抵抗することから、ルクレツィアの想いは届かないというルクレツィアのとても個人的ないき詰まりが描かれます。
人は役割をいくつも担いますが、ルクレツィアもそれに翻弄されてしまうのがこの劇です。
ジェンナロに母であることを名乗れないルクレツィア、名乗ることはジェンナロを精神的にも肉体的にも奈落に落すことになるからですが、その名乗れない歩をしてしまったルクレツィアで、彼女の生涯はとても儚いです。
自業自得でもありますが、一人の子を想う母としては侘しい最期でした。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】マダム・ボルジア 演出:宮城聰

spacの新作「マダム・ボルジア」のテーマは「恋情の復権」です。
宮城さんの演出ノートに「恋情」は“相手を美化することを伴う愛”で、そして、“相手を美化し、それに照らして自分も相手にふさわしい者になりたい”と解説されています。
マダム・ボルジア(=ルクレツィア)は残酷極まりない人物として描かれていますが、唯一息子のジェンナロだけは命掛けで愛しました。
他の人物に対してはあまりにも冷たく、命までをも軽んじても、ジェンナロだけは別です。実はこれは私はとても共感できます。
流石に他人を殺めることはしないでしょうけれど、唯一ではないけれど、ほんの一握りの人だけを大切に想ってしまう気持ちが解るのです。
個人的に、私自身があまり人付き合いをしないということもその理由の一つではあるかもしれないですが、誰にも彼にも気持ちを注ぐなんてことは不器用で出来ないという感覚です。
ルクレツィアもとても不器用な人(女)であったのではないでしょうか?
ジェンナロが死に向かってしまうと、取り乱し、何でもありでそれに抗います。
その姿からは残酷なイメージは欠片もありませんが、でも劇中でも自分を虐げた男5人を平気で毒殺します。
人は多重人格で、多分私もそうなのでしょう。
そしてルクレツィアはジェンナロなしでは生きていけない人で、幼い頃ジェンナロを手離し、いつか再会できることをただただ願い生き甲斐とし、目の前に現れるともう合わずにはいられません。
そして母と名乗れない境遇が仇になり悲劇になります。
ルクレツィアは、ジェンナロを母殺しにさせてしまったことが無念で仕方なかったけれど、それは宿命でもありました。
ジェンナロを気にかけているルクレツィアとそうでないルクレツィアは明らかに違う人物です。恋情(愛)とはかくも激しい感情であり、それを持つことだけでも幸せなのかもしれません。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】メディアともう一人のわたし 演出:イム・ヒョンテク

ギリシャ悲劇「王女メディア」のメディアは元夫イアソンへの復讐のために我が子二人を自ら手がけてしまいます。
それだけ夫憎し、そして、メディアは残忍だったということは誰でも解るけれど、解ると納得は雲泥の差です。どんなにかイアソンへのあてつけかの想像ができないのに言い張ることではないけれど、およそ私にはどんなことがあっても我が子を手がけることはできません。
でもこの悲劇も多くの芸術家がその芸術家の解釈で演出しています。そして、この作品もその一つですが、少なくとも演出家のイム・ヒョンテクさんは、私と同様に我が子を手がけるメディアの心を読めなかったのでしょう。それを逆手にとっての“イム・ヒョンテク版メディア”でした。
メディアを二人登場させるのがこの作品です。
原作通りの残忍で我が子をも手がけるメディアと、どうしてそんなことができるのか、当然ながらメディアにも葛藤があるはずという、我々に近いメディアです。
二人の女優が折り重なる用にメディアの心情を観客に伝えます。
その伝え方は、メディア二人だけでなく、イアソンも、他の登場人物も、その身体と、舞台袖両側に配置されている楽曲と歌で主に表現されます。
それは、観客の心に訴えるという言葉通りで、数多の台詞では表現できない表現方法です。
素晴らしい楽曲と歌声、そして登場人物に合わせた声色、時にはオーバーアクトの演技もありますが、それも殺し合いの運命にある人々のしかも限られた時間で生きる人の生き様として観ると、その異世界を覗いている感覚になります。
そしてなんといっても二人のメディアは、とても精力的であり、母性の塊であり、ですが、実は私には窺いしれない残虐性があるということで、そんな二面性(多重人格)があるようには見えないけれど、しかし、物語の展開は悲劇を正当化するがごとくに進みます。
我が子を手がけるというあっては行けない行為に悩む姿がもちろんありますし、オーバーアクトはそれを可能にするかのようにも見えました。
韓国の古典芸能の楽曲と歌の要素と、現代の音楽の要素を合わせた音響を受けての身体表現=踊りは狂おしくも見えます。
この劇自体がメディアの人格を訴えているのでしょう。
頭にではなく、どこまでも感情に突き刺さるようなそんな劇でした。
【いもたつLife】