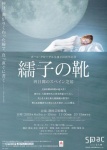いもたつLife
【spac演劇】授業 西悟志 演出

この西演出のSPAC版「授業」は生徒(布施安寿香)がエネルギッシュで、虐げられる女の抵抗を強く感じます。
教授も強力で、教授役は3名、強権発動するいかにも教授(渡辺俊彦)、若手でこちらも生徒に負けないエネルギッシュな教授(野口俊丞)、もう一人道化のような変化球の教授(貴島豪)(アフタートークで、この3人目の教授はジョーカーと内内で呼ばれていたそうです)、三位一体で不条理に生徒に挑みかかります。
冒頭から教授はただものではない雰囲気がありますが、生徒を迎える本当の最初は、その辺のオジサンだったのが段々エスカレートしていきます。生徒に我慢ならなくなり本性が露になるのですが、その悪魔の本性は生徒に挑発されてそれが湧き上がるのではないかと想えたのですがそうではなく、実は誰が相手でもどこかでそれが発動してしまうことが解り、怖ろしい事実で、これは日常にあるのだというメッセージがとにかく怖いです。
でも舞台上はユーモアを効かせています。
基本は生徒と教授の二人劇、それを4人の俳優が演じているのですが、要所に醒めたメイド役が出るのが、この授業の特色でもあります。
メイド役ではありますが、役者としてクレジットされていない裏方の女性で、教授に醒めた台詞を投げかけます。
その台詞と態度は教授に心底ウンザリで、一徹した雰囲気です。
そうなんです。この教授はウンザリするオジサンなのです。
それに抗う生徒を演じた布施さんにエールを送り続けたくなる劇です。
人はやりすぎる生き物で自制がきなかい。
男は自己満足をどこまでも追求する。
愚かしいばかりなこの教授は他人事ではありません。
【いもたつLife】
【グランシップ寄席】 春風亭一之輔・玉川奈々福・神田松之丞

落語、講談、浪曲という日本の三つの和芸を楽しもうという粋な企画です。
開口一番は前座の柳家あお馬さんの「子ほめ」。
滑舌もリズムもよく、すぐに二つ目になりそうな噺っぷりでした。
続いては松之丞師匠です。
演目は「雷電初土俵」ですが、時折挟むアドリブが場の的を射ていて場内が湧きに湧きます。
丁度一年前に松之丞師匠を観ているのですが、さらに腕が上がっていました。
続いては一之輔師匠の「百川」、そして仲入りを挟んでもう一度一之輔師匠の「がまの油」です。どちらも面白いし、好きな演目ですが、一之輔アレンジでもう大爆笑でした。
トリは浪曲の玉川奈々福師匠です。浪曲は初めての体験でしたが、そういうお客様が多いことを踏まえて、浪曲の解説と、楽しみ方と嗜みを、ユーモア込めて玉川奈々福師匠が枕で話してから本番です。
静岡にゆかりがある話ということで、「大井川乗り切り」です。
圧倒的な声で魅了されます。
ところどころの台詞回しは演劇のようです。そして、三味線の伴奏と相槌も見事です。
浪曲侮りがたしでした。
三つの和芸を満喫できました。
【いもたつLife】
花緑の夢空間 第16回

静岡市の駿府城公園で恒例の柳家花緑独演会です。
二つ目の花飛(かっとび)さんの「新聞記事」からスタート。
花飛さんは前座名は、ふらわー(どういう字かは不明)で、前座は仮の名で、
それをカリフラワーと言うという枕も、本番も面白かったです。
花緑師匠はノリノリの枕から「試し酒」、昨年聞いた「猫の災難」でもそうですが、酒を飲まない花緑師匠の酒飲みぶりは必見です。
仲入りを挟み、またまたノリノリの枕から、「井戸の茶碗」、終演まで15分で井戸の茶碗は驚きですが、それだけ師匠本人も言っていましたが、この落語会は、ついつい枕でしゃべりすぎるようです。
ちょっとはしょった「井戸の茶碗」でしたが、もちろん面白い、師匠のこの演目は2度目ですが、前よりもメリハリある落語でした。
追伸
10/8は「寒露」です。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「寒露」の直接ページはこちら
寒露
【いもたつLife】
柳家花緑 独演会

静岡市の江崎ホールで、平沢寺主催のこの落語会も今年で17回目、
私も一昨年から参加させて貰っています。
花緑師匠の落語会は2月以来です。
まずは二つ目の圭花さんの「松山鏡」、
圭花さんは、昨年のこの落語会でも、2月の落語会でも聞いています。
だんだん上達がわかります。11人のお弟子さんのうちの9番目だそうですが、
お弟子さんが上手くなる様を追えるというのも楽しいものです。
その後はもちろん花緑師匠で、いつもの通り枕からノリノリです。
仲入り前のこの時間では枕を挟みながら、花緑師匠にしては珍しい、
新作2作でした。
最初は「謎のビットコイン」(多分)という噺で、5分位の短い落語。
「やかん」をコンパクトにして現代にもってきたような噺で、
リズムも良く楽しい演目でした。
続いては題名はわかりませんでしたが、こちらの新作は師匠が顔芸と声色を
様々駆使した花禄師匠ならではの新作でした。
仲入り後は大ネタの「柳田格之進」。
まさに“たっぷり”と声を掛けたくなるほど力が篭っていました。
花緑師匠は静岡にはよく来てくれます。次回も楽しみです。
【いもたつLife】
【spac演劇】繻子の靴 演出:渡邊守章
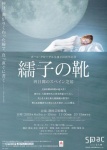
実質8時間、午前11時から夜の8時30分、途中3回の30分前後の休憩を挟み演じられた「繻子の靴」。ここに居合わすことができたことに素直に有難い、得がたい体験だったというのが、観劇後の実感です。
剣幸演じるドニャ・プルエーズと石井英明演じるドン・ロドリッグの悲恋の話なのですが、そこに吉見一豊演じるドン・カミーユの横恋慕、はたまた安部一徳演じるドン・ペラージュが正式な夫という四角関係で、それぞれの人物造形が対話劇で現されます。
また、その四角関係の本筋と同時並行で、彼らの召使たちの恋物語も挟まれます。
原作の抽象的な会話や難解な議論を役者たちは忠実に力強く具現化していて、原作ではイメージできない世界を見事に表現していました。けれどやはりその台詞は難しいというのが正直なところでもありました。
舞台は三層というべきか三階建てというべきか、場面に応じて縦に役者を配置します。またこの舞台は同時にスクリーンにもなっています。この演劇は動きが少ない、会話が中心ですので、人物の配置とスクリーンに映し出される背景(景色や、世界をまたぐ話なので船、また世界地図)により立体感と動きを想像させるという舞台になっていました。
主題は前述した通り、ドニャ・プルエーズとドン・ロドリッグの実らぬ恋なのですが、それは現世でのことであり、あの世というか天国では成就するということで、その証として、ドニャ・プルエーズの忘れ形見の七剣姫の恋は適うという、これが四日目、この演劇のラストに用意されています。
一日目、ニ日目、三日目の時間を追うごとに悲しくなる話とは変っての四日目でした。
また一~三日目には劇の舞台、16世紀のスペインと世界の関係が盛り込まれていて、それもこの劇の見所でもあります。
作者が親日だったこともあり、四日目には日本にも触れられます。
とても長い劇なのですが、ドニャ・プルエーズとドン・ロドリッグが直接語りあるのは三日目の最後だけ、また、ドン・ロドリッグとドン・カミーユの恋敵が直接対決するのも三日目の一度だけです。
登場人物が多く、それらが語る状況で主題を浮き立たせている構成で、そこに当時の(または原作者や演出家)の世界観が盛られています。
当時を現すのは舞台だけ、でもその当時の本当の世界を覗いているような感覚になる。そこには市井の人達もいれば、自己の生き方を主張する力強くも頑固な人々もいます。
500年前に浸っていた8時間でした。
【いもたつLife】
【spac演劇】マハーバーラタ ナラ王の冒険 演出:宮城聰

せかい演劇祭ではもう定番という「マハーバーラタ」で、やっぱり楽しい、素晴らしい劇です。
3年ぶりの観劇、3年前も駿府城公園で、ここでは大きな環、360度が舞台です。
物語はナラ王とダヤマンティー王女の冒険で、国をしっかりと治めていたナラ王が悪魔に取り憑かれてしまい、全てを失い、でももう一度元の偉大な王に返り咲くということですが、ナラ王とダヤマンティーの何が起きてもお互いを信じ合う、どんな状況になってももう一度二人は結ばれることを諦めない、愛と勇気の物語でもあります。
いつも通り、宮城演出が冴えます。
ムーバーとスピーカーに別れ、打楽器に乗ってムーバーは舞、スピーカーは緩急をつけて時に力強い主張を、時にユーモアを、また話のナレーションをします。
どれもspacお得意の職人技です。
ナラ王は聖人君主で、ダヤマンティーは神々も妻に娶りたいほどの気品ある姫です。
そんな二人が奈落の底の落ち、そこから立ち上がる、そんな二人だから必ず大丈夫として観る劇で、大団円に確実に向かうそれが見所です。
演劇祭の華でそして、ありきたりな言い方になりますが、愛と希望と勇気を与えてくれる、そしてspacらしさが詰め込まれているのがマハーバーラタです。
【いもたつLife】
【spac演劇】大女優になるのに必要なのは偉大な台本と成功する意志だけ 演出:ダミアン・セルバンデス

演劇というのは役者と演出家だけでは成り立たないことを、この演劇では招聘するに当たってどうプロディースするか、どうすれば日本でこのパフォーマンスを伝えきることができるか、プロディーサーとスタッフという裏方さんのご苦労が成功を産んています。
選ばれた舞台はかなり古い、昭和30年代にもてはやされた、当時はモダンなレストランで、今は空き家です。
その雰囲気は、その古さになんとも言えない寂れた観があり、メキシコの豊かではない住人が住んでいる一室が重なります。
でもそこはきっとわいわいがやがやで、それを伝えるために入場前に観客にメキシコのラム酒が振舞われます。
狭苦しい待合室で飲むラム酒、場末に来てしまったと感じた後に会場へ。そこはもっと狭苦しい、暑苦しい空間で、観客を詰め込むだけ詰め込んで、二人の女優が演じる舞台は、観客の手が届く近さで、八畳ほどのこれまた狭くて暗い中で、突然始まります。
一人は言い方は悪いですがかなりのデブ。もう一人は対象的なやせっぽちの女性。
奥様と女中で、大声の早口で二人はその立場で言いたい放題、それがひとしきり続くと、実は二人は女優で、役の練習をしていたことが解ります。
終わると今度は、二人はお互いを褒め合います。
でも和気合い合いはすぐに終わり、今度は本気で罵り合いの喧嘩になります。
その激しさは、最初もかなりでしたが、それを超えるもので、よくもこんなに大きな声が、よくもこんなに相手を貶めることができるものだという激しさです。
そんなことは長くは続きません。あまりにもエネルギーが要りますから。
疲れた二人は大人しくなるのと同時に、お互いをまたもや労わり合います。そして添い寝となり終了です。
子供の頃、兄弟喧嘩をよくしたのですが、それが重なります。
すぐに喧嘩、でもそれはひとしきりで、疲れて、仲良くなっても、またいつの間にか喧嘩、その繰り返しだったことが想い出されました。
子供のその頃はその頃で真剣に生きていた結果、それがこの二人、大人になっても純粋で真剣に生きているのかもしれません。
場末の貧しい中で生き抜く力強さと自分の中にある子供の頃の懐かしさが洗い出されて触れた、そして心がなんとなく温まった劇でした。
【いもたつLife】
【spac演劇】シミュレイクラム/私の幻影 演出:アラン・ルシアン・オイエン

小島章司の白熱のフラメンコ、その後準備を整えて、ダニエル・プロイエットが振袖姿になり、しなやかな日本舞踊を披露してくれます。
日本人の小島章司がスペインのお家芸を、アルゼンチン出身のダニエル・プロイエットが歌舞伎舞踊を、しかもどちらも超一流の舞です。
そしてその両方を観劇できる私などは、所謂大衆で、日本は豊かになったということをとても感じます。
演劇や伝統芸能、または音楽ライブに、そして映画や絵画などの芸術に、今の日本では安価に様々に触れることができます。
また情報社会と言われて久しいですが、世界のあらゆる出来事と深い浅いは置いておいて、繋がることができます。
戦後の高度成長前までは、庶民が、こんなに芸術と身近にあることはなかったでしょうから、贅沢なことです。
そしてこの劇ですが、小島章司の子供の頃からを、母との別れを追います。最後の舞踊は彼の母の舞でした。そして彼はその前に、母を想ってのフラメンコを踊りました。
小島章司のこれまでの集大成なのでしょう。
【いもたつLife】
【spac演劇】寿歌 演出:宮城聰

核戦争後の絶望世界、相棒と二人だけでそこにポンと置かれたら自分はどうしているか?
そこにあまり頼りにならない神のような存在が現れたら何をして貰おうとするか?
「寿歌」はそんな境遇ではこんなことが起こっているんだという話で、それはそれは暖かく、人を好きになる、人は強いことを感じる劇です。
ゲサクとキョウコは旅芸人で、リヤカーを引きながらまだミサイルが飛び交う中を彷徨っています。正確には彷徨うのではなく、「ちょっとそこまで」行こうとしています。
何をしながらか、もちろん芸をしながらです。
二人はやたらと明るい、なぜこの世界で明るくいられるかという位に軽い。深く考えること、悩む事、悲しむこと、落ち込むことを通り越してしまったのかとも思えるのですが、それとも違います。
そこにヤスオが登場、彼は二人よりもかなりまともな神経ですが、ヤスオもめげていません。
3人旅が始まります。
その道中、舞台はずっと笑いに包まれます。
くだらない漫才、でたらめな歌と踊り、街にたどり着くとそれを披露するゲサクとキョウコ、そして今はヤスオも入って。
観客はいません。もしかしたらもう二人とヤスオしか世の中には存在していない世界ですから。
でも旅芸人ですから、芸を披露するのです。
とっても悲しいけれど、人はとても崇高だと思える劇です。
頼りにならないけれど、神はきっといて、というか、自分を観ていてくれる存在はきっといて、頼りにならないことも十分承知、といいますか、頼りにならないからちゃんと生きていくことができるのが人です。
もう40年近く前に作られた戯曲で、当時よりも世の中がこの「寿歌」の世界に追いついてきていると多くの人が感じるでしょう。
でも世の中がどんどん悪くなっているかはわからないし、それと自分の生き方は別ですし、どう生きていくかこそがいつの時代もそれが全てで、それを考え決めることが大事で、この「寿歌」もそんなことを提示してくれる劇でした。
【いもたつLife】
【spac演劇】民衆の敵 演出:トーマス・オスターマイアー

温泉がある事で栄えている街のトマス博士は、その温泉が実は汚染されていることを突き止めます。これは世に知らせなければ、で始まりますが、温泉を正常にするのにはべらぼうなお金と、カネのなる木である温泉街を2年間も休みにしなければならないということから、トマスには圧力が徐々にかかります。
トマスの兄は市議で彼の猛烈な反論がトマスにかかります。それはトマスの証拠だけでは信じられないと言う屁理屈を発端とするもので、市議のその意見はトマスに協力的だったマスコミをも隠蔽に向かわせます。
という現代でも、日本でも、堂々とまかり通る内容です。
この話を、市議たちの今を取るという乱暴な主張、対、トマスの正常な主張、という対立から、それを一歩進めた、近代の先進国が歩んできた経済優先ゆえに精神の荒廃が起こり、それが悪であるとトマスの主張は過激になり、原理主義を貫くようになっていき、それと市議たちを対峙させるという構図にこの劇は持っていきます。
その対立シーンが佳境になると、なんと舞台俳優がこれについて、その場に集っている観客相手に議論を促し、実際に論議を交わします。
この実際にありがちな事件を表面だけでなく、その奥底にある、人が人との間で起こる問題はなんだ、という普遍な問題として提起しています。
またここからも出色です。あくまでも世の中は悪意にまみれているといまで迫るトマス、市議たちは確かに自分たちの利益で動いていますし、改めなければならない行為をしていますが、果たしてそれは市議たちだけかと、トマスはどうなんだという所へとトマスを追い込みます。
トマスの義父は地に落ちた温泉施設の株を買い占めます。もう二束三文ですが、大逆転の可能性があるからです。それはトマスが主張を翻すことで、トマスの目の前にはトマス名義の株が置かれます。トマスは妻と共にそれに見入る、それが最後のシーンです。
正義は絶対ではありません。同じ事象が正義と悪とになるから諍いが絶えません。だから温泉が汚染されているのは事実でも、それへの対処は立場と役割でまるで変わります。トマスにとって汚染は許せない事実であったのが、許したくなる立場と役割になる皮肉で終わらせています。なんと意地悪な劇でしょう。
またトマスの原理主義的な主張もあまりにも決めつけすぎです。そこには民衆に対しての操作が裏に隠れています。正義を主張することで支配する立場になっていくという怖ろしさを見せつけています。
私達が生きている社会は、確かに上手く機能しているとは言い難いでしょう。でもそれを解決するのは一通りの正義があれば進むのかと言えばそんなことはあり得ません。そうであれば何もしないできないで良いかと言っている訳でもないでしょう。
ただ少なくとも踊らされることでは解決はないことを示唆しているように感じました。
最初の家庭のトマス家族の平穏シーンから段々不穏になって行くのですが、日和見な他の登場人物を映し、ではトマスの家族は潔癖かというとそうではないことも匂わせるなど、演出は細かく気が配られ、また緩急を付けてもしてとても味があります。また、俳優の演技も鍛え上げられています。そしてテーマも深く素晴らしい劇でした。
追伸
とても個人的な意見ですが、私はなるべく繋がらないことはこれからますます大切になっていくと思っています。自分の等身大で守れる範囲で守りたいモノを守る、利己な生き方でOK、ただし節度が十分にあればです。
【いもたつLife】