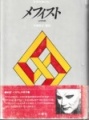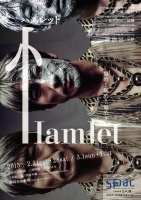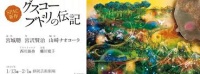いもたつLife
【SPAC演劇】ふたりの女 宮城聰演出 唐十郎作

主人公の光一が、自分が作った自分を囲う檻を壊し、解き放つことができたのが、「ふたりの女」で、誰もが気づかずに自分を縛ってしまっている呪縛があることを暗示させます。
精神病院の医者である光一には、妊娠している婚約者アオイがいます。光一が海辺で、砂浜にラブレターを書きながらアオイへの想いを吐露するところから劇は始まります。
病院には、六条というアオイにそっくりな患者がいます。
六条は何故か光一を愛しています。光一も六条のことが気にかかります。そして、六条から鍵を受け取ります。その鍵は、六条が退院した折に光一が迎えに来るサンドバギーの鍵だと六条は言います。
場面は変わり富士スピードウェイで、光一とアオイは観戦しています。光一はツワリで気分が悪いアオイのために夏みかんを、弟に取りに行かせます。そこで弟は六条とのクルマのトラブルに巻き込まれます。そこに光一が現れて六条と再会、六条は今、化粧品のセールスをしていると言い、東京で仕事をしたいからアパートを探して欲しいと光一に依頼します。光一は不動産屋の紹介くらいなら出来ると渋々請け負い、そのお礼に六条は化粧品を光一に渡します。
アオイは、光一から化粧品を受け取るとそれを使うのですが、それは化粧品ではなく髪油でした。それを付けると匂いが強く取れないとアオイは言いながら、何故か段々と六条のようになったり、アオイに戻ったりします。
アオイの時のアオイは、髪油を誰から受け取ったかを、また、サンドバギーの鍵まで見つけて光一を詰問します。
次の場面は六条のアパートです。光一は眠っているアオイから取り上げた鍵を返しに来ました。そこに不動産屋が現れます。彼はアオイを玄関まで連れてきて、アオイは二人の会話を立ち聞きしていたと言います。慌てた光一がアオイを探すとアオイは崖の上にいます。
アオイは光一を罵りながら身を投げてしまいます。
最後は精神病院です。光一は院長に自分を六条がいた6号室に入れてくれと頼みます。しかしそれは叶いません。すると光一は海辺に出て、亡きアオイに向けての想いを吐露しながら砂にラブレターを書きます。
すると六条が現れます。光一は六条に、なぜアオイと仲違いさせるようなことをしたのかと詰問します。そして、終には六条を絞め殺してしまいます。
私は光一はずっと6号室の患者であったと解釈しました。だから六条は光一が作った幻影です。アオイが亡くなったのは自分に責任があり、それを責める存在として六条が生まれたのではないかと考えました。
この劇では他にも幻影を作り出す人物が登場します。
富士スピードウェイの駐車場係は、居るはずがない酔っ払いの老人を抱えて歩きます。また、彼は自分の中に潜む負の感情を常に外に向けて放っています。そして、彼の兄は入院患者で、自分が犯した罪を償うために指を切り落とすしかない、けれど指は10本しかないことを悩み、11本目の指を探しています。
これらは光一が抱いてしまった強迫観念を他の登場人物も持っているということです。
光一はアオイに赦されたいために六条を作り、六条と対話します。そして六条が自分の目の前から消えた時、光一はアオイを亡くした現実と向き合えるようになったのです。自責の念は消えたわけではありませんが、檻を作りその中でしか生きてはいけないと言い聞かせた自分を、その檻から出ても良いと決着を付けたのが最後のシーンだと思います。
舞台は野外で、舞台の先には天然林があります。
格子状に砂が盛られた観客目線のセットと、その上に廃木の柱が組まれた目線よりも高いセット、そして、天然林を活用した奥深く天に近いことをイメージさせる部分も使われていました。
登場人物が目線のセットと、それよりも高いセットにいることにより、その間柄の親密感や不信感を現していて、アオイが身を投げる時の天然林の部分は、異世界へと旅出つことを強調していました。
また、格子状に盛られた砂が、最初は整然としていながら、徐々に崩れていく様は光一の心情が揺れていくことを示唆し、また誰が砂を荒らすかでもその人物の立場を語るということも同時に表現していました。
ところどころに喜劇の要素を入れながら、事実笑いが起こるシーンが随所にありながら、己が己を縛っているのが人だという、かなり辛辣なことが語られてい演劇でした。
最後に、宮城さんのカメオ出演というサプライズがありました。カメオとは言えない位の長い出演でしかも演技も達者でした。とても楽しかったです。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】 メフィストと呼ばれた男 演出 宮城聰 作 トミ・ラノワ

「メフィストと呼ばれた男」を語る上で、3つ賞賛したいことがあります。
1、 1932年から45年までのベルリンを垣間見ることができる舞台設営
2、 登場人物達の、その時々の心情を語りつくす「劇中劇」の素晴らしさ
3、 なぜこの劇が今上演されているかのメッセージは、作り手が私達に期待を込めていると私は感じたこと
この3つを書きたいと思います。特に3番目は強く心に響きました。
まず舞台設営ですが、実際の観客席を舞台の一部として使っています。
通常は、手前が客席、奥が舞台ですが、劇場を奥から手前に分断しています。だから客席と舞台の左半分がこの劇の舞台になります。観客は右半分から左半分の舞台を見ます。
よって観客は、この劇の舞台になるベルリン国立劇場の舞台と客席を含めた全体を横から見る形になります。
「メフィストと呼ばれた男」の背景は、1932年から1945年までのベルリンです。その間にドイツが歩んだ道を国立劇場の俳優(芸術家)達の姿で語ります。
だから劇では、劇中劇もありその劇中劇の稽古も、揺れ動く情勢での俳優達の不安やこれからの劇団のことを議論する姿も、間近に行われます。
それを覗き見するような感覚での鑑賞です。
第二次大戦でドイツがどうなるかを私達は知っていますから、登場人物達がどうなっていくかも察しがつきます。ですからこの観劇は、覗き込みながらも俯瞰することになります。そのお膳立てができている空間でした。
そしてこの舞台の長所として、横に長い空間も挙げられます。
舞台奥から客席の出入り口までが舞台になりますから、離れた距離の表現が感じやすく、実際、主人公と亡命した女優とのやりとりでは、舞台の離れた位置を活かしていました。
また、為政者は舞台中央上部で、戦争末期で苦しむ市民の代表は舞台左で、亡命した女優の当時の苦悩は舞台右奥でと、3者のやりとりもこの空間を十分活かしていました。
劇の始まりは1932年のドイツのベルリンの国立劇場、そこでは「ハムレットの舞台稽古(劇中劇)」が行われていました。そこにナチスが第一党になった報が入ります。
この劇の主役はクルト。演技の天才でハムレットでは演出家としてもデビューする予定です。共産主義者だったために、ナチスの台頭で自分の地位が危うくなることを気にします。
その時の芸術監督はヴィクターです。彼はクルト以上の共産主義者で、この後、通称「巨漢」と呼ばれるナチスの文化大臣(モデルはゲーリング)に芸術監督の地位を剥奪されます。劇団を去るつもりが、クルトに説得されて役者として残ります。
巨漢がクルトを芸術監督に据えた目的の第一は、クルトにプロパガンダの演劇をさせるためです。もう一つは、クルトの才能をドイツが失うのは、あまりにも惜しいからです。
当日、クルト、ヴィクターと、ナチス党員のニクラスが、演技に関しての見解を発端に、ユダヤ人である主演女優のレベッカを巻き込んだ言い争いが起きていました。ユダヤ人差別をするニクラスに対してクルト、ヴィクターはニクラスを退団させるのですが、ナチス第一党の結果はニクラスの復帰と、逆にレベッカともう一人の主演女優ニコルを亡命に追い込みます。
また、巨漢の愛人で大根役者のリナが巨漢のコネで主演女優になるという布陣で、クルトはナチスの下に国立劇団の運営を余儀なくされます。
ここまでが大まかな前半。後半は、前半の10年後から終戦までになります。
前後半通して劇中劇が多数入ります。戦況の悪化とともに、クルトの苦悩が増していきます。そのクルトの心情は劇中劇で表現されます。
まず、芸術監督に就任した直後は「ハムレット」で、クルトがナチスに迎合していってしまう心は「ファウスト第一部」で、そこから時は進み劇団員のクルトを見る目を「リチャード三世」で、というようにです。
また、劇団員が議論を交わし収拾がつかない状態は「ジュリアス・シーザー」、そして、ドイツが東部戦線で苦戦している頃は、ソ連の芸術を全否定しますが、「櫻の園」等の劇中劇を挟むという演出です。
圧巻は、どうにもこうにも立ち居かなくなったドイツとクルト本人を表現する、クルトを演じた阿部一徳さんの劇中劇のメフィストでした。クルトはメフィストを演じれば右に出る者はいないという設定で、それをそのまま感じさせました。
この劇では劇中劇が多いことに加えて、それが登場人物の心情や、劇中の社会情勢と的確に繋がる役割を果たしていました。
この演劇の原作はクラウス・マンの「メフィスト 出世物語」です。もちろんクルト(原作ではヘーフゲン)の出世が描かれています。「メフィストと呼ばれた男」でもクルトは出世します。
クルトがヴィクターに散々罵られながらも巨漢の招聘に応じた一番の理由は、演劇を続けるためです。ナチスはクルトが芸術監督を引き受けなければ、他の誰かを据えたでしょう。演劇の上演は、民衆を動かすための有力な武器だとナチスは考えていて、それはクルトも承知でした。
クルトが芸術監督として与えられた条件には、演目を選べることをはじめとした、世に溢れる失業している役者も、たとえ共産主義者であっても採用できるという程の大きな権限と、共産主義思考だったこれまでのクルトの過去を一切咎めないという最上級のものでした。これだけの条件ならばクルトは、当時のドイツの民衆に、演劇で喜びを与えることができるという芸術家としての使命と喜びを得られる、そして、それができる第一人者が自分であるという自負もあり、クルトは国立劇団を率いることにしました。
クルトはその地位を活かし、一人でも多くの失業した役者に役を与えることに腐心し、次第に不安を増していく大衆に勇気を与えるために演劇に没頭しました。
ナチスもそんな彼に報いるために、最大限の待遇を与えました。
彼はまさしく出世したのです。豪邸を構えることもできました。亡命先で不自由を経験し、戻ってきた主演女優ニコルを亡命以前の待遇で迎える事をナチスに承諾させる裁量もありましたし、そのニコルと裕福に暮らすこともできました。
彼は、彼が成していることからすれば、贅沢な生活は分相応だと感じていたはずです。でも、ヴィクターやレベッカには、魂を売った姿に映りました。
この演劇は歴史の動きに翻弄されてしまったクルト以外の芸術家達の個々の姿にも言及します。
クルト達の演劇に対して、ドイツ国内の情勢が悪化するに従い、巨漢からの要請はどんどん厳しいもの、自由な演劇を規制することになっていきました。そして終には、ナチスの宣伝大臣(モデルはゲッベルス)が登場し、演目を決める自由さえもクルトは奪われてしまいます。
それに耐えられないヴィクターはナチスに逆らい投獄されます。ヴィクターは魂を売ってまで芸術を続けることができなかったのです。
ナチス党員だったニクラスも耐えられない一人でした。彼は、ナチスこそ労働者を貧困から救える存在だと信じて入党しました。ところが政権を奪取してからは、その導きは幻想だったことに失望します。軍部上層部と、一部のブルジョワが支配する構図は変わらないどころか、増々エスカレートするナチスに敵意を抱くようになり、巨漢と宣伝大臣の目の前で反発します。もちろんそれは死を覚悟してです。
同じく魂を売る引換として今を生きることができなかったのが、もう一人の若い主演女優のアンゲラです。彼女は役者としても人間的にもクルトを尊敬し、慕っていました。クルトが多くの民のために尽くしたことに力を貸すことができることに意義を感じ、それに応じて自らの成長も見出せていました。けれど、ヴィクターやニクラスが葬られることには耐えられませんでした。クルト達とは別の道へ、亡命を選びます。
ではクルトは魂を売ったのでしょうか?私は違うという考えです。
彼は芸術家として秀でていましたが、同時に合理主義者で、祖国ドイツの愛国者です。命の危険を感じた時にも亡命の選択肢を拒みましたし、祖国のためにその時々の状況に置かれた自分ができることを最大限やることに、全力を尽くしたのです。
大局的に考える男で、民のためになるならば、手段は自分の意思に背いてもそれは魂を売ることではないと考えたのです。でも迷いはなかったとは言えないでしょう。当然苦悩の日々だったでしょう。
劇団には、クルトの母ママヒルダもいます。彼女はいよいよ大戦が終わる直前に、クルトの前で苦しみながら亡くなります。また、愛人のニコルも自暴自棄になり戦地へ身を投げ出してしまいます。それらの直後に終戦となります。
そしてクルトは、新総統から引き続き芸術監督の要請をされ、なんとそれを受けるのです。
これまでの経緯を追うと、結果としてクルトはナチスに加担していたことになります。そして目の前で母も亡くします。それでも彼はまた新しい国のために尽力する精神があるのです。合理主義者であり非常に貪欲であり、自信家であり、あくなき闘争心を持つ者です。
平和の訪れと共に、レベッカとアンゲラは帰国します。舞台へ戻ってきてくれたと勘違いして喜ぶクルトですが、彼女達はクルトとの決別を告げに来たのです。彼と相入れる心をとても持てないのです。
劇はラストを迎えます。クルトの思い悩む姿で終わります。
この演劇は、どう生きることが美しいことかを、問いかけている、これが私が「メフィストと呼ばれる男」で最も感じたことです。
それを揺れる時代の芸術家達の姿で示しています。クルトと他の人達との対比で示しているとも言えます。
穢れた自分でいられない、あくまで清く生きたい、そんな想いが強いのが、レベッカでありヴィクターでありニクラスであり、アンゲラです。もちろんユダヤ人であったか、裕福な生まれであったか、貧困であったか、共産主義か、ナチズムに傾倒していたかでの個々の差で、結末の違いはありましたが、皆クルトとは違う美意識です。
クルトに近い存在のニコル、ナチスが栄えていた数年間、彼の意思を尊重し彼を支えたニコルも最後は、自分の過去を自分で拒否して自暴自棄になり、戦地に飛び込み死を選ぶということをします。彼女でさえもクルトとは違うのです。
ではクルト以外は美しい生き様で、クルトはそうではなかったのかとは私は思えません。
クルトは最善を選んだのです。でも仲間からは受け入れられませんでした。
最善を選んだのは、巨漢も、宣伝大臣も同じです。しかし戦犯として生涯を閉じました。最善を選んだのは、民衆も同じです。もちろんナチスに抱いていた、期待していたこととは真逆の結末に、世の中が大惨事となってしまったのですが、ナチスを支持したのは事実です。
クルトも美しく生きようとしていたはずです。でも崖から転がる石が止まらないように、ナチスがクルトの自由裁量を奪えば奪うほど、ナチスが窮地に陥るほど、プロパガンダ色が強い演劇をせざるを得なくなり、ナチスへの加担というレッテルが貼られていったのです。
しかしクルトは投げ出しませんでした。
1932年にナチスを支持した民衆は、この演劇の原作、クラウス・マンの「メフィスト」が出版された1936年にはベルリンでのオリンピックで、ドイツの反映と平和を確信していました。誰がその後のドイツを想像することができたでしょうか?
日本ではたまたま平和が続いています。では今の時点で、近い未来に日本が先の大戦のようなことを起こすことがないと言えるでしょうか、そんな保障は一切ありません。でも、それが起こるとは大衆は思っていません。
この演劇で、第二次大戦に巻き込まれるドイツの芸術家達を覗き見ました。その先の一般市民の格闘と苦悩も想像させる劇でもありました。
演出した宮城さんは、この劇を上演した想いとして、「日本で根付こうとしている公立劇場の存在とは何かを考えるきっかけを提起したい」と言っています。
クルトと同じ立場、公立劇場の総監督としての宮城さんは、私達市民に考える力を養うことを期待してこの演劇を持ってきたのだと思います。
世の中に潜んでいる解らないけれど感じるモノを、芸術は、抽象的ですが提示してくれます。
考える力とは、芸術が語る真意を感じる力、受身でいるだけでなく、自ら察する力を養って欲しいということです。
そして自分自身に美しく生きることを常に問う、それも期待しているのがこの演劇であり、メッセージであると私は思います。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】天使バビロンに来る 中島諒人演出

喜劇ですが、世のために尽くすという心根が、自分さえよければ良いになってしまう人の性を謳う辛辣さがあります。ただし、そこから抜け出せる提示もしています。
舞台は古代バビロン、王は国のために尽くしています。外国には軍隊を派遣して領土を広げます。対国内は富国強兵のために、乞食さえも公務員にして働くことを促します。
国王は、頑なに乞食を貫き通す、たった一人乞食として残ったアッシを改心させようと自ら乞食になります。
そこに、天使がクルービという美しい女性を連れてバビロンを訪れます。クルービは「最も貧しい男」の元に天が差し向けたのでした。
乞食勝負をする王とアッシ、負けた王をクルービは愛するのですが、王はクルービをアッシに渡してしまいます。
アッシはその後宮殿の役人の首吊り男となります。
その頃、バビロンでは市民革命が起こり、宮殿ではどう収めようかと議論が進みます。
国民的に人気を博すようになっていたクルービを王妃にすることで、革命を鎮火させようとする王、首相、教会長でしたが、クルービはあくまでも最も貧しい乞食を探す、王妃にはならないと言い張ります。
そこで教会長は、その乞食は王だったことをクルービに話ます。驚いたクルービは王の下に行こうとしますが、「最も貧しい」のは王ではないとして首を振ります。
そうすると革命を収めることはできません。バビロンは・・・。
王は国民のために、領土を広げ富国強兵を進めます。
その両輪として、政治で支えたのが首相で、思想で支えたのが教会長です。
3人を含め国の首脳は、国を豊かにすることに尽くしていました。けれど、いつのまにか国民の視点とは段々ずれていってしまいます。これはよくあることです。
問題はそれに当人は気がつかないことです。
自らの地位を守るために権力を使い始めてしまいます。
アッシは王の方針、乞食をやめて公務員になることを拒みました。
なくなく首吊り男にはなりましたが、自由を奪われることには用心深くしていました。
だから、バビロンが崩壊することを察すると、国を飛び出していきます。
バビロンは、天の怒りを受けて崩壊するのですが、王、首相、教会長は崩壊ギリギリまで、その座に、権力にしがみつきます。国にしがみつくのです。もう難破船なのに。
国民も同じです。国にしがみつくのです。
飛び出したアッシとは対照的です。
砂嵐の中を懸命に歩むアッシ、その後を着いていくクルービの姿でこの演劇は終わります。
二人は野たれ死ぬかもしれません。でもバビロンにしがみつく選択肢はありませんでした。
アッシは乞食をやりながらもしたたかでした。
機転がきく商売人のようです。首吊り男の時も、王の圧制をかわしていました。
自分自身を失わない存在がアッシです。
だから最後クルービはアッシについていくのです。
自分自身を失わない、その前にバビロンの人々はどこまで自分の存在を知っていたのでしょうか?
自分を見つめるのは基本ですが、とても困難なことです。
【いもたつLife】
「メフィスト 出世物語」クラウス・マン著
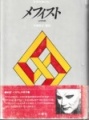
1936年にクラウス・マンが亡命先で書いた、反ナチスの小説です。
主人公のヘンドリック・ヘーフゲンが、明らかにグスタス・グリュルントゲンスであることから、戦後西ドイツでの出版を巡って裁判にもなっている小説です。
ヘンドリックが政治的な思想とは裏腹に、ナチスの最高幹部に取り入って出世するのですが、演劇(芸術)にかける情熱も描かれますが、当時の社会情勢で揺れ動く人々の心の機微が生々しく感じられます。
小説では、ナチスが台頭していく時代から、巨大になったという時間軸です。
歴史を知っているからもう第二次大戦は免れないとして、当時のドイツを想像するのですが、発表されたこの本は著者の警鐘だったことがわかります。
ただ、あまりにも実在の人物と重なってしまったということですが、それもクラウス・マンが祖国をそれだけ憂いていることを感じます。
【いもたつLife】
立川談春独演会 『百年目の会』(水戸)

まだまだ上手くなっていくことを感じる、談春師匠の独演会でした。
ウォーミングアップのような枕から入り、
最初のネタは「替り目」、夫婦のやりとりにより重点が置かれていて、
夫の内弁慶ぶりとシャイに妻を想う心が見事い演じられていました。
そのまま高座で、今回の“30周年記念『百年目』の会”開催の主旨を絡めながら、話を始めます。プログラムでは「談春半生記」となっていましたが、
笑いもそこそこに、師匠の人生観を感じる内容で、
この落語会全体も、談春のこれまでと、これからを、言葉の間で感じる落語会でした。
仲入り後は、大ネタの『百年目』です。
これも師匠独自の解釈を入れての熱演です。
最後の挨拶で、「自分でここまで頑張ってきたと思う時もあるけれど、そんなことはない、自分は育ててもらったんだ。と、50歳前になって実感している」
とおっしゃっていましたが、その想いが込められている『百年目』でした。
素晴らしかったですし、師匠の今後に益々期待したくなりました。
2時間40分の落語会でしたが、あっという間でした。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】ハムレット 宮城聰 演出
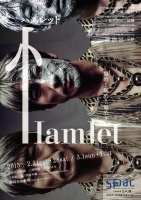
ハムレットは誠実だったのでしょう。それ故に悩んだ。
宮城聰さん演出の「ハムレット」は、ラストに大胆な解釈を入れています。
自国を異国の王に託すくだりで、敗戦国日本を重ねます。
今の日本も悩んでいます。その原因は、あの時から始まっているのは確かです。
ハムレットも、父の亡霊により復讐を命じられてから悩みました。
国を憂いながら悩んだのでしょう。
私は単にどうやって復讐をするべきか、でハムレットが人生の時間を費やしたのではなく、
国を治めるという大事と、復讐することにより自分がなすべきことができなくなる狭間で悩んだのだと思います。
現国王クローディアスのダメな政治は、父を無き者にしたのと同じ位の罪だとしたハムレット。
また、母のガートルートに対しても、安易な再婚の決断を許せないとしました。
狂人のふりをしてまで、愛するオフィーリアを寄せ付けず、自ら成すべき事をやりぬくハムレットは、どうみても、真剣に生きる人物です。
そして武石守正さん演じるハムレットは、愛情深く、聡明で、力強いハムレットです。
そんなハムレットでしたが、クローディアスの画策とはいえ、全てを失う結果となってしまいます。
無念極まりない最後です。
その中で、国のことを想い、異国の王に国を託す決断をします。
それが、宮城演出では、敗戦直後の日本になるのですが、
日本の決断は正解だったのでしょうか?
答えは「どちらでもない」です。
ハムレットが悲劇で人生の幕を閉じたように、悲劇として終わっても終わらなくても、
生きる苦しみは常に誰にでも訪れます。
確かに戦後日本は繁栄しましたが、それが続かないことは今誰もが感じています。
人生の喜も悲も、生きてきたある部分を切り取っての結論であって
どちらかなんて、決めるものではありません。
それよりも実感として残るのは、自分に対して誠実だったか、
ダメダメな自分にしては良くやった方か、そんな感触だと思います。
武石さんのハムレットはとても立派ですが、それでも もがいていました。
私のような凡人はもがいて当たり前です。
もがき苦しみ、悩み、でも一歩進む。それで良いではないか。と思える観劇でした。
【いもたつLife】
古典ムーヴ・春爛漫【S-5】

柳屋三三師匠、柳屋花緑師匠、立川志らく師匠、の贅沢な落語会でした。
三人のおしゃべりから始まり、一気に会場は盛り上がります。
演目は、三三師匠が、タイムリーな長屋の花見。
三三師匠は初めてでしたが、実力がありました。
花緑師匠は、何度も見ていますが、益々バワフルになっていました。
枕も絶好調。
演目は、井戸の茶碗。時間内に本当に上手くまとめました。
この落語会は、2日間にわたり5回開催されたのですが、その大トリが志らく師匠で、大ネタの文七元結。
志らく師匠も何度も見て、大ファンです。もちろん大満足。
実力派師匠三人の充実落語会でした。
追伸
3/6に、3月の「毎月お届け干し芋」出荷しました。
今月のお宝ほしいもは、“ほしキラリ丸ほしいも”です。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
毎月お届けの「今月のお宝ほしいも」の直接ページはこちら
今月のお宝ほしいも
【いもたつLife】
今年の蔵見学

菊姫会総会の後、これも毎年蔵見学していきます。
並行複発酵という日本酒の仕込みは、大変複雑かつ繊細で、
菊姫酒造では、細かいことにまで神経を配っています。
蔵見学もゆうに10回以上ですが、毎年新しい発見があります。
【いもたつLife】
第12回菊姫会総会

昨日と今日、菊姫会総会が山代温泉で開催です。
毎年参加しています。
昨日は日本酒の勉強、唎き酒、懇親会と盛りだくさん。
今日は総会と蔵見学です。
【いもたつLife】
再見 【SPAC演劇】グスコーブドリの伝記 宮城聰 演出
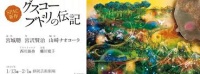
「心が洗われる」なんて言葉を安易に使いたくありません。
けれどこの演劇は、その言葉を言いたい心境にさせてくれます。
けれど同時に、崇高な心でいたいなんて想いは、
すぐに日常に紛れてしまうことを深く感じることにもなります。
素晴らしいSPACの演劇「グスコーブドリの伝記」を再見することができ、
観劇が終わるとそんなことを考えました。
初見では、演者、舞台セット、音楽、照明を含めた演劇自体の完成度と、
どんな演出かということに夢中になり、また、グスコーブドリの生き様、すなわち宮沢賢治がどんな心境だったのか、そして宮城聰さんの解釈はどうか、またどうやって具現化するのか、それらを私がどれだけ受け止められるかに心を砕きました。
でも今回は、この演劇から何を受け取ることができるのかと、自分の心の動きを意識することになりました。
自分は残りの命を何に使うのだろうか?
グスコーブドリのように、イーハトーブの人々のために、平然と人知れず尽くす。
誰もができないことをやっても偉ぶることもなく、限られた命に対して嘆くこともなく、
生を全うすることは到底無理です。
なんてたって、このような素晴らしい演劇を観て、人に対しての思いやりの心が目覚めても、すぐに常の自分に戻るからです。
でも、グスコーブドリは大きな世界を対象にそれができる人物だったけれど、もっと小さな世界の中であれば、私でも彼と同じ心境で同じようなことができるかもしれない、または、少しだけならやっているのではないかと、立ち止まって自分を観てみることができました。
最初にこの演劇で強く感じたことは、グスコーブドリはいつも等身大だったことです。
再見して、そうか、等身大な自分でいることができれば、自らの心も安らかだし、今よりも少しはましな生き様になることが、自然にできるかもしれないと痛感しました。
ラストのメッセージでは、人は人へ繋ぐことができるでした。
なりたい自分になれず、結果を残すことも出来ずに人生が終わっても良いのです。
その過程で身近な人が何かを得て、良きことを繋ごうとするからです。
「グスコーブドリの伝記」を観て、やっぱり人は最終的には善な存在だと思います。
だから今の世も本当はもっと生きやすいのかもしれません。問題なのは、今の己を飾ってしまう心なのでしょう。
追伸
2/6に、2月の「毎月お届け干し芋」出荷しました。
今月のお宝ほしいもは、“いずみ薄切りほしいも”です。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
毎月お届けの「今月のお宝ほしいも」の直接ページはこちら
今月のお宝ほしいも
【いもたつLife】