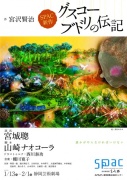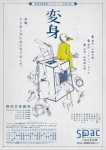いもたつLife
【SPAC演劇】グスコーブドリの伝記 宮城聰 演出
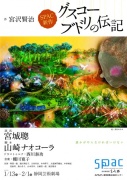
宮城聰さんの解釈ですが私には目の前に広がる世界は宮沢賢治の世界そのものに見えました。
グスコーブドリはイーハトーブに一生尽くしました。けれどそれはやれることをやるという等身大で、いつも心安らかでした。
自然は人のことなどおかまいなしです。何の意志もなくバランスをとっているだけです。人は知恵を絞りその恩恵を得ようとしますが、時になすすべなく絶望を強いられます。
グスコーブドリはそんな厳しい自然といつも対峙していました。
その中で、我は何のために、誰のために、何をしたいのか、それを貫きました。
闇に浮かぶ白を基調としたセットと幻想的な音楽で冒頭からイーハトーブの世界に引き込まれます。
グスコーブドリの一生という長い時の流れを、シーンとシーンの間に闇を入れてテンポよく進めます。そして闇から現れた瞬間に、何が起きているかをすぐに感じさせる演出で、私はグスコーブドリの心情に注意を注ぐことができました。
彼の一生は悲劇に見えます。努力に対してあまりにも報われなかったからです。でも本人はそんなことどうでも良かったように見えます。その強さは自分に対しての嘘偽りのなさがもたらしています。
人は自分が何をしたかを自分が一番知っています。だからどれだけ真摯でいたかは解っています。ただ顔を背けているだけです。
そんな、自分に面と向った姿が宮沢賢治だったのでしょう。
幻想的な舞台上ですが、イーハトーブは生きていくのに辛い現実と同じ世界です。その場でグスコーブドリは等身大でできることを、またそれに呼応するように他の演者もできることをひたむきに演じます。
架空の世界からの問いかけですが、だからこそ、自分の現在の生き様を見つめてみようという気になります。
耐え忍ぶ生き方よりも、結果がすぐに出ないことに我慢できない今、自分の感覚以外は受け入れない風潮を強く感じる昨今で、宮沢賢治の世界に浸れることは貴重です。
そしいていつも宮城さんの演劇で思うことは、観客を信じ応援してくれることです。
宮沢賢治はイーハトーブを理想郷としました。理想郷とは安楽でいられるところではなく、自分を研鑽できるところではないかと感じます。でもその奥底には暖かい思いやりがある世界です。そんな宮沢賢治の世界が表現された希望があふれる演劇でした。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】変身 小野寺修二 演出
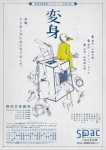
原作が原作ですから、辛い物語ですし、割り切れない、やりきれない気持ちになります。
ある朝毒虫になってしまったグレゴール、しかし彼は虫の姿の人間です。
家族は当初グレゴールは虫の姿になったグレゴールとして捉えていたのが、
虫として扱うようになります。
そこには、愛や良心や善だけでは生きていけない社会の仕組みが隠れていますし、
人の心も、世の中も無常ではないという非情な真実でもあります。
グレゴールも家族も、いっそのこと、彼が心まで毒虫になってしまった方が良いと思ったでしょう。
また、最後のグレゴールの悲劇を考えると、人の心が鬼であった方が、良いのではとも思えてしまう怖ろしさがあります。
そしてグレゴールを失った家族は、まだ生きていかなければならない、グレゴールを失ったことを後悔しながらも、虫になってしまったのだから仕方がないことを自分達に言い聞かせるでしょう。
遺された人の宿命で、これも真実です。
そんな理不尽な内容を、この演劇では、人が重なり合うような動きで表現していました。
明暗がくっきりとした照明の中で、登場人物を強調する際、何人もの役者が重なりながらの演技になります。
SPACの俳優達はその身体能力を活かし、整然・毅然とした動きで観客に迫ります。
その動きを見ていると、虫になってしまったグレゴールよりも、グレゴールとどう向き合うかを迫られた家族の苦悩の方がはるかに揺れるものなのだろうと思えてきました。
もちろん、絶望となったのはグレゴールですが、家族であるグレゴールを厄介者としてしまう心の葛藤が描かれていた舞台だと感じました。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】ドン・キホーテ 原田一樹 演出

夢かなわず、ドン・キホーテは病に伏せ、終幕になるこの演劇を観て、
世の中は人一人が生きる時間では、その人が望む形には変わらないのだとも、
でも確実に変化は起きているとも思いました。
そしてこの演劇では、そもそも現実とは何か?と問いかけてきます。
風車を怪物と決めつけ突進するドン・キホーテ、彼は世のため人のために真剣に行動します。ただ、的外れな独りよがりです。それを諌める回りは良い迷惑です。
ではドン・キホーテだけが独りよがりなのか?とは言えないと、映りました。
実は、現実を見ているドン・キホーテの従者のサンチョも、キホーテを心から心配する姪のアントニアも、アントニアに頼まれてキホーテを連れ戻そうとする司祭と床屋も、意識してはいないでしょうけれど、その行動は、自分自身のやりたいこと(都合)でしかありません。
キホーテの目には想い姫として映るアルドンサなどは、その最たるもので、彼女はキホーテから讃えられる存在ですが、悪しき生き方を一向に変えようとはしません。
頑固で独りよがりはキホーテだけではないのです。
そして誰もが望む生き方や、望む環境があり、それとの違いで悩んだり苦しんだりします。
でも世の中はなかなか変わることはないのが現実です。
(だから巷では自分が変わればと言います)
何年も前の自分の写真を見ると、今ととても違うという体験は誰もあるはずです。
日々目に見えない変化でもそれが重なると大きく変わっていて、振り返ると時代が流れていることを確認できます。
だから変化しているけれど、問題はそれが、自分や社会が望む形なのかということです。
世の中そんなに上手くはいきません。
ドン・キホーテが玉砕していく姿が重なります。
また、この演劇では最後に操り人形のお芝居がど真ん中で映りました。(舞台上の真ん中ではなく、空間上の真ん中)
なにか、キホーテをはじめ、皆が、結局は大いなる力で操られていることを表現しているようです。
それを思うと、現実を見りことができないキホーテも、現実を捉えている他の人物も、
本当の現実なんて見ていないし、捉えてはいない、どちらも五十歩百歩といわんばかりです。
人が生きる辛さを感じるシーンでした。
でも人間はキホーテのように、風車に向っていく存在なのです。
だからやっぱり人間賛歌であることをこの演劇は訴えているのだと私は受け止めました。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】Jerk 演出 ジゼル・ヴィエンヌ

1970年代のアメリカ テキサス州で、10代の若者が27名殺害されるという事件の犯罪者達の行動を非常にリアルに再現した心が大きく揺れる演劇です。またその手法に驚嘆もします。
役者ジョナタン・カプドゥヴィエルの一人芝居ですが一人で6役を賄います。ジョナタン本人は共犯者デイヴィッド役を演じますが、主犯のディーンともう一人の共犯者のウェインと、被害者3名を、人形を使ってジョナタンが演じます。ですからデイヴィッドがこの演劇の進行役兼主役で、デイヴィッドと両腕の人形、それに加えて腕の人形が掴む人形が登場人物になります。それぞれの役は声色を替えて腹話術を使い、ジョナタンが演じ分けます。
一人の演劇、人形での演技では細かい設定の説明はできないことから、観客は配られた冊子で事件現場の背景を把握してから芝居がはじまります。
まず第一幕は、ディーンの殺害の再現からはじまり、ウェインがディーンを殺害してしまうまでです。
その後舞台が変わることから、もう一度冊子を読み次に進みます。
第二幕は、ウェインが次の被害者のブラッドを殺害し、最終的にデイヴィッドが決着を付けるためにウェインを殺害してしまうまでです。
そしてデイヴィッドの告白で事件の全容が明らかになり、この演劇でも再現されたことを説明して終わります。
ディーンは被害者を滅茶苦茶にし、犯しながら人を殺めます。そして被害者を自分の見立てた人物に変えて嬲る。言葉ではしっかりと説明ができないですが、言葉にまとめるとこうなります。
そしてその傍らでは、デイヴィッドとウェインの同性愛のセックスが行われています。これらだけでも衝撃なのに、カメラまで回っています。
これらの一連の出来事を、デイヴィッド本人としてと、人形と数種類の声色での台詞でリアルにジョナタンが再現します。リアルというのは、観客が思い描いてしまう心の中の情景がリアルということです。
この演劇が周到なところは人形劇だから大筋を表現しているだけなので、現場の状況の様子は観客の頭が描くところです。もし映像であれば目を背けたくなるような動きや台詞でも、観たことで納得しようとする、納得して体に纏わりついてくる恐怖や違和感を過去にしようとするのですが、この手法だと、殺人現場は自分で作った像なので映像よりも心に残るのです。
園子温監督の映画「冷たい熱帯魚」でもかなりおぞましい描写がありましたが、私はJerkの方がはるかに気分が重くなりました。こちらは殺人と死体損壊に加えて、ディーンの、殺人が快楽になり常習していくことも描かれているからもあるからですが。
人を憎んだり恨んだりは誰もが持っている感情です。だからと言って通常それが殺人に繋がることはまずありえません。しかし殺人者が、それらが動機だったと説明したら想像ができないことはありません。
けれどこの惨劇は彼等3人が楽しみながら犯しています。その気持ちは全く想像できません。
ただ、27人もの被害者が出たことは、ディーンは人を嬲りながら犯しながら殺人をすること、被害者を違う人物に見立てて葬ること、それをすることで彼の中に強烈な快楽が起こっていたのではないかと推測しました。そうでなければ理解できません。
いくつもの禁忌を破ってしまうことに加えて、他人のアイデンティティーを破壊する行為にこの上ない享楽があったのではないかという推測です。
ウェインがディーンを殺害した時も、ブラッドを殺害した時もそれを匂わす表現がありました。そして恐ろしいことに、ウェインはディーンの代わりの怪物になってしまったことも見逃せません。
この事件が起きたことに深く悲しみ、それを心の中で再現したことの動揺もありましたが、鑑賞後に、私が我を重ねてみてという観点から振り返ってみたら、とてもショックを受けたことがありました。
“人間には他人のアイデンティティーを破壊することを好む性癖があるのではないか”ということと、殺人の快楽がディーンからウェインに伝播したように、その行為はある者が行うと別の者に伝播していくのではないか?と私の中で仮説になったことです。
自分勝手に他人を見立てる行為は軽い気持ちで行ってしまいます。しかもそれを面白おかしく人前で披露することも取り立てて珍しいことではありません。個人的な話になりますが、自分の思い込みで他人にあだ名を付ける、という行為は何度となく行ってきました。
考えてみるとそれも、他人のアイデンティティーを侵食することに他なりません。
そして下手に誰もがそれを認めることになるとそれが伝播します。
この演劇の主犯ディーンも共犯のデイヴィッドもウェインも全く共感できないし理解しがたい人物だということは変わりませんし、許せない犯罪です。
けれど自分とは全く違う人物であるということに捕らわれていたのではないかとも思いました。罪もないことではあっても人を傷つけることで快楽を得ようとしている自分がいることに気づいたからです。またひとつ嫌な自分を見つけました。
けれど見つけた価値はとても高く、気づいてよかったとも痛感しています。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】タカセの夢 演出 メルラン・ニヤカム

世界を代表する一人の少年と九人の少女が、
大人になり老いていくのですが、私達は彼と彼女らにどんな社会を提供しているのでしょうか、と問うてくる演劇です。
スクリーンには、平和に尽くした人々から、犠牲になった人達や、
現在の都市(東京)の状況、そして少年少女にとって当たり前にあるはずの牧歌的なイメージまでが映されます。
それに合わせて彼等は、ミュージカルのように歌い踊ります。
それが全編全力なのが印象的です。
まるで、
僕等はこれ程までに一生懸命に生きていると伝わって来る程の熱気を帯びた姿です。
劇中のダンスは世界各国の基本的なものでしょう。
子供の頃の遊びも挟まれますが、彼等の成長の比喩であるとともに、「かごめかごめ」や「ずいずいずっころばし」等の日本のものが中心で、これらは観客に共感を呼びかけやすい配慮です。
また最初の衣装から10人が十人十色で、世界を象徴していることを示唆していて、彼等の成長期も老いてからもそこに繋げていることからも、観客である私は世界中の子供達とどう関わっているかを考えます。
大袈裟にそういうことを考えるというよりも、どんな気持ちでいるかを優しくでも、真剣に考えるように促される、そんな舞台でした。
タカセというのは、紅一点の反対の唯一の少年の役名です。
彼が夢見ているものは、もちろん世界が仲良くなることですが、
この演劇では、最初に観客と触れる場面があります。
その時からちょっと大きめのトランクバッグがキーになっていて、終盤には、そのトランクバッグには、彼の人生の全てが詰まっていることがわかります。
その中身は、みんなが仲良くなるための道具でした。
そして、それを介して少年少女時代に仲良かった10人が、大人になり離れ離れになっていたけれど、また仲良くなります。
そこでこのお芝居は本来なら終了ですが、カーテンコールで、観客も巻き込んで劇場が一体となる憎い演出があります。
これこそが、タカセの夢です。
夢とは実現していない状況です。
この演劇に“夢”という題名が付いていることを受け止めなければなりません。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】マネキンに恋して”ショールーム・ダミーズ” 演出 ジゼル・ヴィエンヌ

一人の男と、マネキンに扮した女優が器械的な踊りだけで表現する演劇です。
本当に踊りだけで台詞は一切なし。唯一劇中に歌が挟まれるだけです。
舞台には十五体以上のマネキンがいて男とともに七体のマネキンが、
一人で踊ったり、男と戯れたりします。
マネキンは皆極端な身なりや踊りです。
濃い化粧、高いヒール、体のラインを強調した衣装、
意志はないけれど、与えられた役目をキッチリとこなす踊りを見せるマネキン達、しかも個々に個性的です。
観客、特に男の観客の気をひこうとする仕草の踊りで演劇は始まり、
そこから男との戯れやマネキン同士がぶつかるようになっていきます。
一見は成長しているようですが、機械的です。
だから意志があるようには思えませんでした。
でも知性は育っているようです。でも感情はどこまでも封印されています。
だから意志とは、知性だけでは全く機能しないと改めて痛感します。
題名は「マネキンに恋して」ですから、男とマネキンの愛を描いているのですが、不毛に見えます。
演劇後のアフタートークで、
原作は男が月の光を受けた彫刻を見て恋したことをモチーフにしていると知りました。
すると、やはり男が女に対しての憧れと期待をマネキン達に求めていたことになります。
すると、この演劇は私個人として腑に落ちてきます。男が理想の女像を求めた世界です。だから複数の違う個性のマネキンが男と戯れます。
男は時に親密に、時に乱暴な振る舞いです。また、マネキンを動けなくしたりもしますし、操ろうともします。
隠していたい欲望が垣間見れたり、優しく振る舞う姿も見せます。
でも男はやっぱり操作した支配では、マネキンに息は吹き込めなかった。そう映りました。
「マネキンに恋して」は、ロマンチックな男が味わう現実を表現した演劇ではないでしょうか。
追伸
5/21は「小満」でした。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「小満」の直接ページはこちら
小満
【いもたつLife】
【SPAC演劇】隊長退屈男 演出 ジャン・ランベール=ヴィルド 翻訳・翻案 平野暁人

人は期待されるとそれに応えようとします。それは素晴らしいことですが、それによって悲惨な想いをしてしまうこともあります。
太平洋戦争では自国でも他国でも理不尽で非人道的に多くの犠牲者が出て、今もって苦悩する人もいますし、様々な切り口で反戦が唱えられています。この作品も優れたその一つとして数えられるほど、大胆で綿密に作られています。
この演劇では、人が壊れていく様があまりにもリアルでした。
今の日本に居られることが幸せであることはわかりきっていたことで、
当たり前になっていく認識もありました。
でもそれは時が経つのだから仕方ないことだという気持ちでしたが、今回それが吹き飛びました。
以前、知覧の特攻平和会館で当時の若き特攻隊員の遺書を読んだ時に、死を覚悟した後に自分の心を清く昇華させる若者に畏敬の念を抱きましたが、その域に到達するにはどんな葛藤があるかは想像し難いものでした。
特攻に志願するまでのいきさつは、戦前の教育が仕向けたからだとか、集団であることが特攻への合意を拒めなかったとか、自国、ひいては親兄弟のためであったからだとか、要因はたくさんあったでしょう。また特攻以前の問題で、召集されたところから、死は拒めないという状況もあったでしょう。
そして、本でも演劇でも映画でも、当時の事実や人々の生き様も多く語られてきました。
もちろんそれを知ることは大事だという気持ちも持っていましたし、汲み取ることもしてきたつもりです。
「隊長退屈男」では、死しか待っていない緊迫化の中で、いつ死を迎えるかもわからない状況下で心を清く保とうとすることやそこへ行き着こうとする葛藤の凄まじさを目の前に見せられました。そこにあるのは、私が知覧以来感じた想像し難いものの描写でした。
演劇は狭い櫓の上での一人芝居です。櫓はたった一人生き残った日本軍兵、磐谷和泉隊長の砦で、武器はもちろん水や食料や酒も備わっています。外界と唯一通信できる電話がひとつ置かれています。
磐谷隊長が軍歌と共に参戦するところから、徐々に戦況が悪化していって、通信も途絶え孤独になり、恐怖に耐えながら戦い抜きますが、死を迎えてしまいます。
台詞は詩が基本になっています。詩に例えた台詞で磐谷隊長が気持ちを吐露します。時に激しく言葉を発し勇ましい態度を取ったり、時に悲しく、また嘆いたり、怒ったり、怯えたり、また己を鼓舞させるために勇壮な自分を演じたりもします。
国や家族の期待を背負って今、ここで戦っていることを誇りに思うことで、切れかけた精神の線を繋いでいるかのようです。
悲劇なのは、日本の軍人としての威厳を保とうとする方向にしか思考も態度も向かないことです。
「人生は素晴らしい」という言葉を何度も発します。嘘偽りではありませんが、いつでもどこでもどんな時でも「人生は素晴らしくなければならない」と決めています。
この演劇で当初、磐谷隊長は一糸乱れずに纏った、本人も送り出す側も誇りとしていた軍服姿だったのですが、一枚一枚剥ぎ取るように脱いでいきます。
軍人の磐谷隊長は彼自身の一面であり、恐怖に怯えたり、家族を思ったり、欲望を持っている素の磐谷が当然します。そこには人としての弱さがあることを、軍服を脱いだ磐谷も磐谷だと観客に伝えているようです。けれど軍人以外の自分を認めることを頭が拒むのです。最後は褌一丁になるのですが、そこまできても拒みます。
もうひとつ「俺を揺さぶるのはやめろ」という言葉も何度も出てきました。たった一人なのに、誰かに、何かに磐谷は心をかき乱されています。とても悲しいことです。
軍人として果てることができない自分自身を許せない、またそれを望まれて戦地に来ているという周りの期待に応えることができない自分自身に心を揺さぶられています。
今まで信じてきた生き様に抗うことはなんと難しいことなのでしょう。
戦争の原因は行き過ぎたナショナリズムだと言ってしまうのは簡単です。でも個々人にとっては大事なものを守り抜くことに通じていたり、家族の期待を一身に背負い、それに応えた必死な生き方だったこともしっかりと認識しなければなりません。
良い悪いという一般論は抜きにして、戦時中、国のために戦った方達はやはり、親兄弟、妻、息子、娘のためだから死を覚悟できたのではないでしょうか。
だからボロボロになっても生きている限り人間は、自分のためだけでは生きられない、人との繋がりが生命線なのです。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】真夜中の弥次さん喜多さん 演出 天野天街

こんなに笑ったのはいつだったか思い出せませんが、次に同じくらい笑ったら、その時は「真夜中の弥次さん喜多さん」を観て以来だと思い出すことができるほどの演劇でした。
上映時間100分余り、次に何が起こるかワクワクしながら舞台に釘付けになりました。
まず設定が奇抜です。
時は江戸時代、弥次さんと喜多さんはホモセクシャルで愛し合っています。そして喜多さんは重度の薬物中毒(弥次さんは軽度の薬物中毒のようです)、だから二人とも自分が何者か見失っていて、また何が本当かがわからなくなって幻覚も見てしまいます。
そして、二人にとって江戸は「薄っぺらな街」でしかなく、どうやって生計を立てているかは解りませんが、それは置いておいて、誰もが持つ自分がおかれている今の閉塞感を打破したいと漠然と感じているところに、「お伊勢参り」の広告が出てきます。
薬物中毒から立ち直ることも含めて、全てを解決するのにはこれしかない!ということで旅に出ることを決めます。
一部屋の中だけの二人芝居です。
舞台は「お伊勢参り」に出る前の喜多さんの部屋なのか、旅の途中の宿屋なのか、時間も空間も意図的に明らかにされません。そして、観客にも時間と空間の区別がつかない感覚へと誘う演劇です。それを極上の笑いで巻き込むところがこの演劇の味噌です。
とにかく掛け合いもアクションもリズムが良いから乗ってしまいます。手品のように色々なところから小道具が出てきますし、照明と映像を駆使してもいます。
そして内容ですが、時間が戻ってしまう繰り返しのパートがいくつかあります。
短いパートは、部屋の畳にスイッチがあり、それを踏むと数分前に戻る現象が起きることを二人は発見します。そこで喜多さんは死の世界を見に行くことを思いつき、何度も自殺をします。シュールでブラックユーモアな題材ですが、あまりに辻褄が合わないことを合わせようとする姿とテンポ良く進む台詞で明るい笑いになります。この短いギャグをこれでもかと繰り返すのですが、ギリギリ面白さを外さない回数です。
また、大掛かりな繰り返しもあります。
弥次さんには見えて、喜多さんには見えないものがあるという設定で、アイフォンでうどんの出前を注文する所から始まるのですが、これが長いパートで、時間が戻る時点では見ている方はどこがこのパートの最初のシーンだったかがわからない位です。それで最初のパートで、本当の出来事なのか、喜多さんの幻覚か、または弥次さんの夢か、と注目していると、繰り返しが起きて、再度演じているパートは、ではそっちが本当なのか、それとも二人の幻覚なのか、と複雑な入れ子構造になっています。
でもそれがまた面白いから、次はどんな展開になるのかと身を乗り出します。
終始笑いが絶えないのですが、終わってみると二人が、馬鹿げた繰り返しをしてしまうことも、自分が何者がわからなくなっていたことも、薬物中毒だから二人がこんな男達なんだではなく、二人は何も特別ではないということにふっと気づきます。
空から下界を見ることができたら、多分我々の日常は弥次さん喜多さんとなんら変わりないでしょう。
そもそも自分が何者なんてわかっているつもりになっているのが私達です。そして自動反応のように毎日ほぼ同じような暮らしをしています。朝起きたら着替えて歯を磨き朝食を取る。たまの休みは演劇を観るかもしれませんが、日常はだいたい起きる時間も寝る時間も含めてやっている事は大体同じ繰り返しです。
弥次さんも喜多さんもちょっと前のことは覚えていないコミカルな人物ですが、これだって自分を振り返れば同じようなもので、昨日何を食べたかなんて思い出せるか疑問です。
そしてお互いに見えるものと見えないものが違うということだって、私達の物の見方と同じです。自分の主観で物事を見たり聞いたりします。認知的不協和もその好例です。
考えて見れば時間軸もあった方が便利だから人が作った観念で、生物は子孫を残すことが目的で死ぬまで日々繰り返しな生き方が当たり前です。
この演劇では、人間て面白可笑しく、そして愚かな存在だと鑑賞中感じていましたが、それが自分自身だということにちょっとショックではありましたが、でも人は日々の繰り返しに疑問を呈することができる進化できる存在であることに誇らしくも成りました。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】マハーバーラタ~ナラ王の冒険~ 演出 宮城聰

この演劇の大団円は、力強いリズムに乗せて、演者全員が揃っての観客を心強くさせてくれる圧巻の声明があり、体中の血が騒ぎました。ありきたりな言葉になってしまいますが、この大団円で感動しました。自然に瞼にも涙が浮かびました。
世界中の人が仲良くなることなんてできない現実がありますが、せめてこの演劇を観た人達は家族や友人にもっと優しくできるでしょうし、少なくとも私個人は「もっと仲良くしよう」と心の中で叫んでいました。
物語は東西南北の4つの国のひとつ、西の国のナラ王と、ダマヤンティー姫の婚礼から始まります。ダマヤンティーは人間界だけでなく、神様達も后に迎えたいほどの身も心も美しい女性です。けれど姫の心を射止めたのはナラ王で、失恋した神々までもが、この婚礼を祝福しています。
けれど嫉妬する者はいるもので、悪魔のカリはナラ王を許せません。
二人は二人の子宝に恵まれます。また、ナラ王の手腕で国も栄えている幸せの絶頂でした。カリはこの時点でナラ王を地獄に落とします。
ここからナラ王の冒険が始まるのですが、冒険はダマヤンティーも同じです。ナラ王は賭け事に狂って堕ちた自らを責め姫を実家に戻すために身を引きます。ナラ王はいつか姫を迎え入れることができるようにと泣く泣く姫と別れます。
森に残された姫も、体一つのナラ王も苦難の旅が始まります。
演劇はスピーカーという台詞を語る演者がいて、それに合わせてムーバーという演者が動きます。サイレント映画を立体にしたような感じを受けます。
そこにリズミカルな演奏が加わり野外劇場に木霊します。
衣装は全員がアイボリー一色の衣装を纏っています。劇場の背景は山ですから、自然の木々が目に入ります。薄暮になるに連れて衣装は照明に照らされて浮き出てくるように見えます。
この演劇は、ムーバーとスピーカーもしかり、衣装も本物とは遠くしています。また、衣装以外に白いトラや白い蛇、そして象徴としての鼻だけですが白い象が登場し、活躍します。それらを含めて自然の中に白い衣装が映えている様を見ていると異空間にいるような感覚になります。だから見えていない情景が見えてきて心を撃ちます。
ナラ王が森で姫と別れる時、姫の片袖だけを持ち去ります。姫といつも一緒にいられるようにです。目覚めた姫は王がいないことを悲しみます。
二人の演者はムーバーですから動きだけで表現します。スピーカーからの補助はありますが、あくまで観客は動きに注視します。
また、姫は森で蛇に食べられるという危機に合いますが、旅人に助けられます。けれどその旅人に今度は付け狙われます。王も裸一貫で流浪の旅です。
それらを簡単に見せるのですが異空間にいることで、二人の心中を探るのです。
またかなりユーモアを含めた展開なのも特徴です。日本語での言葉遊びもありますし、観客を巻き込むサービスもありますし、時事ネタも巧妙に入れています。
そんな楽しい演出とリズムに乗ってクライマックスへと進みます。
ナラ王は自分の一番の得意技の馬術を駆使して姫を迎えるチャンスを得ます。それは同時に国を失った賭け事はカリの策略であり、カリに憑かれていたことが原因であり、カリに憑かれることを拒むことにもなります。
この物語は、あきらめないこと、準備しておくことのメッセージが込められています。そして最も発信したいことは、信じることです。
王はいつか姫を迎えようと心に決めていました。それと同じく姫も王が迎えに来ることを信じていました。王は醜い姿に変えられていましたが、姫はその姿でも王を見極めることができます。王の迎えを信じて疑わなかったからです。不安な日々を過ごしていたはずですが、不安と信じないは別です。
不安だけれど信じていられるということは、王を想う気持ちの強さです。当然同じほどに王も姫を愛していました。
だからこの演劇は、純愛物語でもありますし、大団円で感じた印象は、二人の純愛物語を下敷きにした世の中を愛する気持ちを持ちたいという愛の演劇であったと私は想っています。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】ファウスト第一部 演出 ニコラス・シュテーマン

すごい演劇を観た。というのが鑑賞後に浮かんだ言葉です。
主要登場人物は、ファウスト博士、悪魔のメフィスト、ファウストが一目ぼれするグレートヒェンですが、役者3名がこの3名の人物を固定しているわけではなく、3名が時にファウストを、時にメフィストを、時にグレートヒェンを演じます。主な受け持ちがありますが、固定されていません。
ファウストという人物は、またグレートヒェンの苦悩の内は、ということを、縦横無尽に役が入れ替わることで観客は固定された人物からの受け入れを拒まれます。
人は置かれた立場や状況や、誰と対峙しているか、またその時の本能を含めた欲求で、様々な気持ちになり態度を変えます。それを現しているようです。
多くの方々がファウストを世に出しています。その数だけの解釈があります。この演劇ではファウスト博士が直情な人物として描かれます。学問を修めた達観な人とは少し趣が違います。嫌らしいメフィストに近いとも言えます。
だからファウストは欲望ゆえに堕ちていくのではなく、自分と戦っている人物像に映ります。これは投げ掛けで、個人的には自己の内を見せられている気分です。
それは理屈を優先させている前半の台詞にも大きく現れています。
また冒頭にドイツの演劇は何でもありと宣言して始まり、徐々にそれが露になりますが、ここも私が心の内を観るということを感じたことに繋がってきます。
だから、鑑賞は心を抉られるような体感になります。
しかしそれとは間逆な美しいソプラノが奏でられます。
この演劇は人間性の否定ではないとも感じる瞬間でした。
またメフィストはグレートヒェンに絡まるように体を接します。悪魔ですからメフィストはグレートヒェンの目に見えることもあり、姿を見せないこともあると解釈しました。体を絡める時は見えないときでしょう。でもそれでもグレートヒェンはメフィストを嫌悪します。
ファウストを愛しながら友人のメフィストを嫌うのは、姿を現さない時の嫌らしさを感じ取っているからですが、ここも人への言及で、人が人を観るのはその人の存在そのものであり、言葉や行動ではないことを強調しているかのようです。
3者が3役に別れる演出と素晴らしいソプラノだけでなく、補完のための映像が時折挟まれるのも特徴的でした。
役者の演技も含めてかなり高度なことが盛り込まれていることを強く感じます。一度では捉えきれないことが多くあったことが残念なほどです。
だから鑑賞後に浮かんだ言葉が“すごい演劇”だったのだと思います。
【いもたつLife】