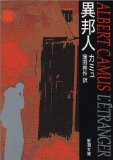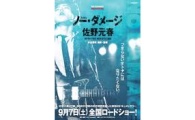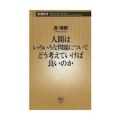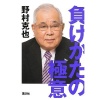いもたつLife
【SPAC演劇】サーカス物語 作 ミヒャエル・エンデ 演出 ユディ・タジュデイン

人の尊厳への問いと、現代社会への風刺と警告、そして人が生きるために不可欠な愛し愛される愛の物語ですが、私が感じた一番のことは、『自分を偽らなくても良いよ』という許可を得る演劇でした。
劇中劇が終焉に至る時に、あの完璧な存在とされたアングラマインでさえ自分を偽っていたことに衝撃を受けたからです。
物語は、二重の螺旋構造で進みます。
主人公達のサーカス団は、人びとから必要とされていないことからの行き詰まりに直面しています。唯一打開できる選択はスポンサーである化学工場の広告塔となることですが、その条件は団員の一人である障害者のエリを排除することです。何故ならエリは化学工場の責で障害を負ったからです。
団員達が明日からの糧の確保を選ぶことで失う代償は、一生消えない自らの品位を落とす行為です。
そんな差し迫った現実の中でもエリは無邪気にピエロのジョジョに物語をせがみます。優しいジョジョは、エリと自分との愛の物語を作り聞かせます。この劇中劇がサーカス団の現状と彼らが下さなければならない決断への葛藤の様になっていきます。
劇中劇はエリ王女とジョアン王子の物語です。“明日の国”の王子ジョアンは、大蜘蛛アングラマインに国を奪われます。ガラスの城にいるエリ王女は、魔法の鏡カロファインが映すジョアンに恋します。エリ王女は城を出てジョアンの下に行くかを悩みます。何故ならエリ王女は、ひとりでガラスの城にいる限り、何の不自由もなく、しかも不老不死だからです。ジョアンを探すことは、人としての苦悩を背負うことになります。しかもジョアンと相思相愛になれるかも、そもそも出会うことができるかもわかりません。
でも、エリ王女は城をでます。
現実世界では団員達がエリを捨てるかの選択を迫られます。何故捨てない選択に躊躇してしまうのか、それは捨てなければ生きられない強迫観念が襲うからです。たしかに経済的には苦しくなってしまうのですが、そんなものはあくまで虚構です。現代人はあまりにも物質に頼り過ぎてしまいました。生活する上で必要でないものまでが、無ければならないと教育されています。それは他の人達が持っているから?あれば安心だから?それはあくまで表層的な理由です。本質的な理由は、心を満たすために人と触れることを避けようとすることです。モノがすぐに手に入るのをいいことに、物質で心を満たそうとする行為です。その方が簡単だから。そして、これも自分を偽る行為です。
こういう現代社会の構造は、アングラマインが支配する明日の国と同じです。明日の国では人は蜘蛛の巣に手足を縛られて生きています。その姿は無駄を捨てること、効率こそが優先されるべきであるとされること、そして人がそれに合わせるものだという社会が作り上げた幻想概念で縛られていている我々の姿そのものです。
しかも劇中劇のエリ王女もジョアン王子もアングラマインにより、過去の記憶が消されていました。私達は本来の喜びを想像できる力があることすらも封印されていることの暗喩です。
物語は、サーカス団がギリギリの選択を迫られて、にっちもさっちもいかなくなる境界線に追い込まれた時に、新しい展開になります。
障害者のエリはエリ王女だった。ピエロのジョジョはジョアン王子だったことを、二人は愛し合っていたことも想い出し、現実世界から劇中劇のアングラマインが支配する明日の国へと足を踏み入れます。
この展開ももちろん、現実世界でサーカス団が化学工場とどうやって立ち向かうかの決断への葛藤に繋がります。
それにしてもミヒャエル・エンデは人の愚かさを認めながら、崇高さも信じているようです。エリは知的障害者であり、ガラスの国の王女です。ジョジョもピエロであり、勇敢なジョアン王子です。どちらかではありません。どちらも彼ら自身です。
この社会では人が持つたまたまの一面だけでラベリングすることが行われています。それは愚かな暴力であり、それが発動されている世を嘆いているかのようです。
その後演劇は、エリとジョジョがエリ王女とジョアン王子に戻り、サーカス団員と共に“明日の国”を奪回するためにアングラマインに戦いを挑みます。観客は二人と彼らの活躍を期待する場面です。
しかしアングラマインの下に行く前に大きな谷間ができていました。谷間は彼らを阻みます。この谷間はアングラマインが作ったのではなく、ジョアン王子の意識でできたものだと明かされます。ここもエンデの皮肉です。弱者にも過ちがあるのです、強者は過ちだけではないのです。
ジョアン王子は「愛と自由と創造」でアングラマインを倒します。ここでもう一度現実に戻ります。エリとしてジョジョとして、サーカス団も化学工場の要望を受け入れなければ明日がないこの演劇の振り出しの現状へ戻ります。
アングラマインをやっつけたって、もちろん何も変わっていません。
でも団員全員の意志で、化学工場との契約書を破り火にくべます。後を絶ちました。絶望を選んだようにも見えます。彼らの目の前は苦で満ちたことを暗示させて幕になりましたから。
彼らが何を選んだのかは明白です。“偽らない自分”を選んだのです。その時に彼らは自由を得る体験もしました。たとえ目の前に迫る現実が物質的な困窮から逃れても、自分を偽る限り自由は得られません。逆に自由を得ても困窮という状況は何も変わりません。しかし今まで持てなかった希望を得ることができます。
絶望の中では希望を持てないのではありません。絶望と希望はどちらか片方しか存在しないのではないのです。
“自分は何者か”そこから逃げないことが生きる根源で、生きている証なのです。
【いもたつLife】
異邦人 アルベール・カミュ 著 窪田啓作 訳
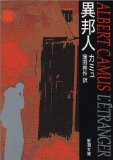
「一人の平凡人の長所が、どうして一人の罪人に対しては不利な圧倒的な証拠になりうるのか」
「ひとはいつも、知らないものについては誇張した考えをもつものだ」
主人公ムルソーが何故銃を撃ったのか
「それは太陽のせいだ、といった」
ムルソーは己を客観視しています。
何故なら、彼がかかわるあらゆる人との関係が、あまりにも虚飾だけだから。
彼は聞かれたことに対して、それ以上でもそれ以下でもない本心を話すと、
答えられた方が戸惑うことが最初から最後までこの小説に詰まっています。
聞き手はいつも答えて欲しいことを答えて欲しくて聞きます。
御大層に大真面目に。
ムルソーはそんな世界と決別したかったのかもしれません。
たとえば災害に合った時、
もし一人ならすぐに逃げる行動をとります。
もし十人でいたとしたら、一番遅い十番目の人に合わせて逃げることになるでしょう。
社会が機能している状態というのは、そういうことです。
不条理であることを、『そんなことはない』と全員で大合唱しているようなものだということを、改めて強く強く感じたのが率直な感想です。
もちろん常日頃私自身もそれで社会からの恩恵を受けています。
でもそういう仕組みであり、
そういうルールであることは心得ていなければなりません。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】愛の終わり(日本版) 作・演出 パスカル・ランベール

心が通じていない者同士の間では、言葉なんて無意味で通じないもの。
心が通じている者同士では、言葉なんていらないもの。
だとしたら、言葉は単なる伝達の機能しか持たないものなのか、でも人は時に言葉を尽くして相手に自分の想いを伝えようとします。
この演劇でも、多くの言葉が飛び交いました。無意味なものから、自己を代弁するような体中から絞り出すような言葉まで。
でも心が離れている間の仲では心には響かない。でも言わずには要られない。言葉を手に入れた人の性なのかもしれません。
演劇は別れ話です。男と女が今の心境を相手にぶつけます。
ただし一捻りあります。会話は常に一方通行です。男が女に発する時は、女はすべてを受け取るしかありません。反論はもちろん、聞かない選択もできません。女が男に発する時は逆になります。
そしてそれが前半の男の言い分と後半の女の言い分に分かれます。
表面上は罵り合い(正確には一方的な罵りです。長いスパンで罵り合いになります)ですが、裏側には別れの儀式をお互いが行っています。
男は延々と自己肯定、他社(女)否定します。裏側にはいかに愛していたかに通じるのでしょうけれど、とてもそれを第三者が察することができません。ほとんどが抽象的な記号の羅列です。そして終始一貫続けます。思い浮かぶ言葉がなくなるまでそれを続ける姿は、まるで何かに怯えるようにも見えます。
女は男の言葉を受けて、記号の羅列をあざ笑いますが徐々に様相が変わります。
もちろん女も自己肯定、他者否定の立場でいました。けれど、それだけでは収まらないようなのです。同時に女の言葉を受ける男も自分で自分の体を支えられなくなります。
時は過ぎ、女の言葉が尽きた時なのか、お互いの気が済む時に終わりを約束していたのか、二人は静かな沈黙を守り対峙します。これまでの形相とは違い、見つめ合い幕になります。
二人の別れが完成したのです。
この儀式を設けて、お互いと自分を痛めなければ別れられない二人だったことにようやく気が付きました。その時に愛が深かったことも感じました。
演劇中ずっと言葉は無意味だと感じていました。そして最後の二人の別れの完成でも無意味だったことは間違いないことを確かめられましたが、無意味だから意味がないのではないことが解りました。
お互いを否定する言葉でも、相手を怒らせたいことだけが趣旨でも、記号の羅列の応酬でも、それをやること、もっと言えば言葉を交わすことに意義があったのです。
言葉を無理やり捻り出しても相手の心に響くことはありません。解りあえているほど言葉なんて要らないのです。
そしてこの二人も相手の気持ちなんて、とうにわかっていたのです。そしてもう別れなければならないことも、それが最善の選択であることも。でもきっぱり関係を切るために儀式が必要だったのです。
今までの二人の愛の大きさ、想いを、言葉に乗せて時間かけて交わさなければ別れが成立たなかったのです。
人はどんなに理屈で納得していても次に進むことができません。人だからこそ、生きている生身の人間だからこそを表現した演劇でした。
【いもたつLife】
<松井久子の生きる力>松井久子 著

「生きる力」は養っていくものだと改めて気づきます。
それでも世の中はだんだん厳しくなりますから、「生きる力」はより必要になりますし、時と共に個人も守るものができてくるので、より強くが宿命です。
著者は優しく強い人です。そして己をよく知っている。
著者ほどではなくても、自分がどれだけの自律できる力があるか、今からでも、もっとそれを養うことを真剣に考えてしまいました。その先に自立があることも説いてくれていますから尚更です。
そして“人”を冷静に観ています。良い面も悪い面も含めて。その良い面も悪い面も好き嫌いではなく、人とは(男とは、女とは)そういうもんだとして捉えています。
良い悪いは、その場その時に現れることですから、普遍的ではありません。だから冷静に、“今人は”(連綿と続いてきた人の営みのために)「こういうもんだ」という観かたです。それは、男・女としてや、日本・他の国は、という視点からです。
だから、仕事のやり方も王道を貫いています。
どうすれば世に受け入れられるか(需要があるか)、それが的を得ていたとして、世の人に共感(消費)されるようにするにはどういう切り口にすれば良いか、そして、その仕事を現実にするために、高い次元を目指します。(あなたにはできないと世間に言われる仕事を目指す)
著者自身も書いていますが、『切った張った』を突っ走って来ました。その著者が日本(人)の現状を改めて振り返ると、ため息ばかりではないかと感じます。(少し触れています)
その落差の感じ方こそ、どう生きてきたかで、個人個人異なることなのでしょう。
私の感じている尺度との違いは想像するしかありません。
すると、やっぱり、「もっとしっかりしなさい」と遠まわしに言われています。
とにもかくにも、「生きる力をつける力」をつけることから始めます。
【いもたつLife】
佐野元春 Film No Damage 2013日 佐野元春 井出情児
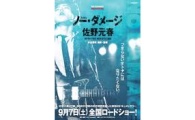
とてもラッキーなことに、80年のデビューからずっとリアルタイムで、
佐野元春さんの音楽とともに生活しています。
当時自分も若かったから、彼の音楽以外もたくさん触れていました。
振りかえってみれば、今は彼だけが30年以上経っても私の隣にいます。
彼は歌で、ライブパフォーマンスで、ずっと生き方を導いてくれている存在です。
その彼の貴重なフィルムが蘇りました。
もちろん懐かしいし、嬉しい、感動ものでした。
そして私自身が33年前から真っ当に生きてくることが出来たかの
試験に臨んでいるひと時でした。
【いもたつLife】
色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹 著

主人公、多崎つくるは20歳の時に、死をも覚悟する体験がありました。
それから16年、その体験を封印していましたが、
どうにもこうにもこのままでは居られないと、恋人(沙羅)から諭されて、
自分に起こっていた過去の事実を探る旅にでます。
その旅はつくるに何をもたらすか?
という物語です。
凄惨な事実とそうでなければ説明しきれない人の愛憎劇です。
つくるは高校時代に、男3人と女2人のグループに属していました、形成していた、の方が正確でしょう。
そのグループは、生産的、建設的であり、理想郷を具現化していました。
普通の高校生では体験できない素晴らしいグループで、形成する仲間は自分も他の仲間も誇りにしていました。
それが突然崩壊します。
つくるは、自分自身を色彩=特徴がない男と信じていました。ただの平凡な男だと。
仲間のアカは、優秀な男です。背が低いことから頭脳明晰が際立つキャラクターです。
アオは、典型的なスポーツマンです。これ以上の説明は彼を解りにくくします。
女性の一人シロは、お姫様のような存在です。可憐で儚い、男が守るべき愛すべく女性です。
もう一人の女性クロは、明朗快活な女性です。シロがお姫様だけに、クロの方が実際はモテたかもしれません。
つくるはある日アオからの電話で理由も告げられずに、グループから除外されます。もちろん、つくるには心当たりはありません。
あまりにも素晴らしいグループに所属していたことから、この疎外感はつくるには耐え難い仕打ちでした。
この日から16年間、沙羅に諭されるまでつくるはこのことを心に、封印していました。
もっと言えば、死を覚悟した半年間を経て、その後の粛々した日々、修行僧のような生活により、あの体験を乗り越えたと自己判断していました。
でもそんなことは有り得ないと、沙羅も読者も感じています。
そこでグループの4人と向き合うことを決めます。
ここからはネタバレになります。
私の書評ではおこがましいので、ここまでにします。
でも一言、
この小説のラストでつくるは、自分を取り戻します。
過去を肯定します、腑に落ちたのです。
自分の振り出し位置を深い闇から見つけることができたのです。
大人になったつくるが振り出しに立つことができたのは読者への希望の灯をともす、著者の応援なのでしょう。
【いもたつLife】
人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか 森博嗣 著
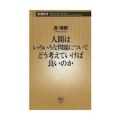
人が自分の幸不幸を計る尺度は、相対的です。
他人がいて自分がいるという立場をとります。
幸不幸だけでなく、楽しい悲しいまでもそういう傾向があります。
人は考えることを嫌がります。面倒だからです。
尤も考えるだけでなく、すべての状況で楽を選ぶのが本能ですから仕方ないことです。
この本では、抽象的・客観的に物事を考えることを、提起しています。
それをすることによってモノの本質に迫ることができるからです。
ではモノの本質になぜ迫る必要があるのか?
ということですが、
私は、自分の内面を観る行為になるからだと思います。
自己の内が少しでも解れば、相対でしか自分を計れない姿勢の自分を、
多少ですが俯瞰できるようになります。
ここでもう一度、なぜ相対から脱しなければならないのか?
それは圧倒的にその方が健康的だからです。
(それを無意味と捉えることに反論はしませんが)
そして、それができる可能性があるのは、人間だけです。
また、自分が作り上げた虚像に対してもそれに振り回されることに対しても、
敏感でいようとも言ってくれています。
だからこの本の提言は、古代から人が生きるテーマとしていた、
いかに死を迎えるか(生きるか)です。
ただし、いつも考えることを気にしていよう。ができても、
考える癖が出来たからといって変わらないかも、とも言います。
期待しないで良きことを面倒がらずに続ける。
案外それ自体に幸せを掴むきっかけ隠れているものです。
著者は、『庭』を例に諭してくれています。
考えることをしないのは勿体ないことです。
考えることで体で起こしている行動が今までと同じでも意味が変わります。
新しい開拓が起こるのです。
今が今まで以上に貴くなります。
同意はできますが、それを満喫している著者が羨ましい限りです。
【いもたつLife】
立川志らく独演会

志らく師匠の独演会は一年ぶりでした。
二つ目の志らべさんの『あくび指南』からスタートです。
大真面目で“あくび”を指南する師匠と指南される落語におなじみの男のやりとりですが、
こんな奴らがいるという設定、
そして、観客と同じくそいつらを覚めた目で見るもう一人がいてというお噺で、
その設定どおりを演じていて、好演でした。
志らく師匠の枕は、談志師匠の話から、
そろそろ三回忌が近いことと、テレビドラマになったことと、その裏話です。
もちろん面白くおかしいネタでした。
演目は『粗忽長屋』志らく師匠らしい膨らみを随所に織り交ぜていて流石の出来です。
けれど私は、『粗忽長屋』は全盛期の談志が落語史上ダントツという男なので、
やっぱり比べてしまいます。
まあ不足だったということではありませんが。
中入り後は『浜野矩随(はまののりゆき)』、
初めて聞く人情噺でした。
芸達者な志らく師匠の人情噺はほろ苦く、時折の笑いが哀愁を引き立てます。
落語はやっぱり良いですね。
ただ、平日ということもあるのでしょうけれど、
結構空席があり、次があるかな?というのが気がかりです。
【いもたつLife】
負け方の極意 野村克也 著
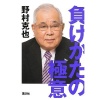
落合元監督の著書でも感じたことですが、
成功するプロ野球の監督のマネジメント(この両者に限ってかもしれませんが)
は、ビジネスでの心構えそのものです。
その考えに新しいものは一つもありませんが、
疎かにしてはいけないことも一つもありません。
凡人だからこその嗜みが詰まっています。
努力を目的としないこと、
一足飛びに結果がでない当たり前、
(考え実践したことが即正解である訳がない割り切り)
教えすぎない、
そして、何よりも我を知る。
弱者はしたたかでなくては生き残れません。
【いもたつLife】
治作 2013年8月

先付
石川コイモ、ジュンサイ、ウニ、オクラ、長芋そうめん、
真夏の暑さが良かったと思わせてくれます。
サッパリで、食欲が湧いてきます。
長芋は昆布締めの一手間と、千切りの一手間です。
ウニと汁も絶妙です。
もちろんジュンサイもオクラも。

ゴマ豆腐
これも夏は格別。
上手いのを解って食べて上手いから凄いのです。
食べて思います。夏も上手い。

うなぎ蒲焼き飯
「時季がちょっと遅いですが」と言ってだしてくれましたが、
土用の丑でうなぎを食べていなかったので、
大歓迎です。
実が締まっている上等のうなぎです。
モチコメで頂く治作流です。

お造り
ハモ、黒ムツ、コチ、赤身と中とろ、アカイカ
私的には前半のメインイベントです。
ハモ、嬉しい夏の味覚です。
コチも夏ならでは。
イカはアカイカ、いつも食べてるイカは何なんだです。
黒ムツも夏に合う。
赤身と中とろは文句なしの大満足。

お椀
もちろんハモです。
これを食べにきたのかもしれません。
中には凝ったレンコン餅です。
すったレンコンにつなぎに片栗粉、百合根も入っています。
これが華を添えています。

八寸
岩牡蠣、枝豆、マメサザエ、レンコンとショウガの白和え、モロヘイヤとエノキのおひたし
今日の真夏の暑さは『このためか』と、
最初に戻ります。(戻るのは私、一貫して夏のもてなし)
夏野菜は今、体が欲します。
それよりも、夏野菜料理がどれも上手いのです。
白和えは、適度に冷やしている心遣いが嬉しくて、またそれで旨味が増す味付けです。
おひたしも適度に冷されていて、隠し味の良い酢が適度に利いていて、ホッとします。
そして、岩牡蠣も夏を圧倒します。(すだちをたっぷり絞りました)
小さいサザエも夏を主張します。
野菜が優しい、貝は主張という方法での美味しさの提供です。

焼き物・揚げ物【鴨】
サッパリ仕立てでやわらかい、これも夏仕様ですが、
旨味がタップリで、鴨好きには応えられません。
(付け合わせのネギと辛子が素晴らしいんです)

焼き物・揚げ物【甘鯛唐揚げ】
頭丸ごとを唐揚げに。
骨までしゃぶり尽くせます。
頭は硬派、エラしたはやわらかな味で、どちらも甘鯛の王道です。

焼き物・揚げ物【太刀魚】
とっても食べやすい演出です。
身はすぐにほぐれるように、
子は堂々に食べれるように、
焼き物という料理、素材を引き出す方法は、微であることを強くかんじます。

炊き合わせ
満願寺唐辛子、トマト、巻き穴子、賀茂茄子
夏のものたっぷりです。
期待よりもちょっと冷たいのが粋です。
そして、これも素材ごとに一仕事しています。
そして、これも夏野菜が主で、サッパリとを具現化していて、
そして、旨い仕立てでなんですね。
料理は芸術です。

素麺
もうこれしかないです。
こんな美味しい素麺を、来る度に食べられる幸せです。

デザート 水羊羹
ギリギリで型を保つことが旨さに直結するということを体験です。
控えめな甘さ、程よい舌ざわり、とろける自然さ、
今回も最後まで見事でした。
【いもたつLife】