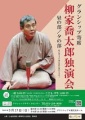いもたつLife
【SPAC演劇】 白狐伝 宮城聰 演出

昨年の「天守物語」とも親和性がある、人間と異世界の者との愛の物語です。
ヤスナに命を助けられた白狐のコルハは、恋人を喪い傷心のヤスナのために、グズノハ姫に化けて尽くします。子まで設けた二人ですが、クズノハ姫が生きていることがわかりコルハは身をひきます。
コルハの献身に涙が溢れます。観ていて異世界(獣だ)なんて関係なしです。これがメッセージでしょう。いつも世界中のどこかで常にある諍いに対してのです。
劇自体は宮城演出そのもので、役者はムーバーとスピーカーに別れてそれをいかんなく発揮します。そして打楽器を中心とした音楽と、衣装や照明を含めた美術も世界観を演出します。
今回はそれを基礎に、歌舞伎の味付けが施されていました。
主演の美加里はコルハとクズノハ姫と、コルハが化けたクズノハを演じ分けます。これがまたまた素晴らしかったです。
追伸
5/5は「立夏」です。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「立夏」の直接ページはこちら
立夏
【いもたつLife】
【SPAC演劇】 友達 中島諒人 演出

川島雄三「しとやかな獣」を彷彿します。笑うに笑えない非常にブラックな喜劇を。
そして男を食いものにする7人の家族の圧倒的なパフォーマンスは演劇ならではです。
また凄まじいまでにこみ上げてくる嫌悪感はミヒャエル・ハネケ「ファニーゲーム」を彷彿させられます。
支配と搾取は最低の行為で、それを平然とやってのける、平然と、それをみせられることは不快が極まります。
それを引き出すのだから、この劇に、造り手の思惑通りになったということです。
不条理、理不尽は自分と社会の間の遠くない隣に潜んでいます。いつ出会わないとも限らない。
平穏な日々は奇跡だと言っても過言ではありません。
素晴らしい劇でした。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】 楢山節考 瀬戸山美咲 演出

凛としたおりん、孝行息子の辰平、そしてもう一人 玉やんを主に演じる役者3人の楢山節考で、不足部分は朗読で補われています。
映画化された二作品も観ていますが、生々しさはこの劇には適いません。
そしてチェロの演奏がそれを加速させます、
役者3人の身体から湧き出る演技と台詞も鬼気迫り、こちらもそれに呼応してしまいます。
映画化された二作品も素晴らしかったですが、この劇も掛け値なしに傑作です。
そして、死を受け入れる、残る者に与えきる生き方は、棄てられない現代でも、いかに死ぬかの人間に課せられた宿命は変わらず、年を重ねるごとに迫る死を自分の中で決着つける、おりんを目指すことは死を(生を)全うすることだと改めて心に刻まれました。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】かちかち山の台所 石神夏希 演出

SPACの舞台芸術公園は、日本平の中腹にあります。そこにはお茶畑もありますが、自然も残っていて原生林もあります。その舞台芸術公園周辺を“かちかち山”にみなして、麓をおじいさん、おばあさんの農家とみなして、化けた狸やウサギ、そしておばあさんが茶畑、お寺、柿の果樹園、野菜畑に出没します。観客はかちかち山から降りて狸たちがいる寺や畑に行き、彼らの動向(演技)を探りに行くという演劇です。
麓に降り、散策し、また登るという2時間の行程はちょっとしたハイキングで、要所要所で狸たちに出くわします。
そして何故、狸が捕まったのか、狸はおばあさんを騙し、婆汁にしたことは罪なのか、を、狸の立場、ウサギの立場、おばあさんの立場から検証する=彼らの言い分を聞くというのが骨子です。
狸は、騙したことも悪戯もそして捕まって食べられてしまうことも、それは生きているからこそと、飄々と言い放ちます。妙に説得力があります。
ウサギも我が道を行くと言いながら、自然の獣たちと人間との折り合いの付け方に一家言ある様子です。
おばあさんも騙されたこと、食べられてしまったことに怒りも悲しみもあまりなく、節理だから仕方なしという立場です。
そして最後に狸たちは音楽のパフォーマンスでもてなします。スタッフも、昔話を想わせる“粟餅”や“豆ごはん”“狸ではない鳥汁”でもてなしてくれます。
大人も楽しめる、運動が入ったお伽話の世界を演出してくれました。
【いもたつLife】
【四月大歌舞伎】

一、於染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)
二、神田祭(かんだまつり)
三、四季(しき)
二作続けて、片岡仁左衛門、坂東玉三郎が出演するという豪華さで満員でした。
於染久松色読販での悪夫婦は憎み切れない悪玉で息もピッタリ、引き立て合うご両人です。物語も面白く、二人に焦点を当てながらも劇としての見応えもありです。
人気の演目だけあり、よく出来た話です。
次の神田祭は祭で出会った鳶の頭と芸者です。二人が出ずっぱりで踊りと仕草で付かず離れずからの愛情表現をします。とてもよくできたサイレント映画の演技のように二人の気持ちと、鳶と芸者という人物を言葉がない方が伝わってくるという演技に歓心します。
それでもって江戸の祭りの雰囲気があります。
ラストの二人の仲睦ましさに拍手が鳴りやまないほどでした。
四季は春夏秋冬の4つの舞踊です。
春はお雛様とお内裏様と五人囃子が踊り出します。おもちゃのチャチャチャのようですがとても艶やかです。
夏は大文字の送り火を背景の舞踊で、秋は夫を想う妻の踊り、冬は木枯らしが吹き木の葉が舞う中でのみみずくと木の葉たちの踊りです。
どれも日本の四季の風情が醸し出されています。
若手歌舞伎俳優勢ぞろいで、こちらも豪華でした。
【いもたつLife】
シネマ歌舞伎 刀剣乱舞 月刀剣縁桐

室町時代の終わりに未来から歴史を変える悪者が来ます、それを追って食い止めるのが刀剣男子です。
SFものですが、内容は全くの歌舞伎で、物語は解りやすく、アクションも多く、また若手歌舞伎俳優がこぞって出演していて、見どころも多かったです。面白かったです。
【いもたつLife】
【柳家喬太郎 独演会】グランシップ寄席
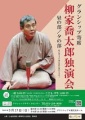
地元、島田市出身の二つ目柳家小太郎さんの「道具や」からはじまりました。リニアモーターカーの枕も面白かったです。仲入り後の柳家喬志郎さんも牧之原市出身でやはり枕は地元ネタ、演目も「その名はおてふ」次郎長の噺でした。
喬太郎師匠は仲入り前が「禁酒番屋」、最後は新作の「銭湯の節」でした。
かなり好きな喬太郎師匠の大好きな「禁酒番屋」そして浪曲を大題材にした「銭湯の節」を堪能しました。
ますます腕が上がっていることも感じました。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】ばらの騎士 宮城總・寺内亜矢子:演出

改めて観劇して、登場人物たちの嫌らしさ、強かさを苦笑いです。と言うよりも笑えませんでした。
人間というのは、ほとほと自分が可愛いのです。そして楽して大きな果実を求めるもの、まさしく自分そのものを見せられてしまいました。
野生の肉食獣は、獲物にありつくまで、じっと隠れて忍耐強くチャンスを待って待って仕留めます。それも紙一重です。大きな果実を得るために努力しないで楽しようなんて考えません。
獲物にされてしまう草食動物も命がけで生きています常に。
生きるためにギリギリでいないから、楽して贅沢を夢見てしまうのですが、どこまで行ってもそれは幻想です。
そして今現在上手くいっているとしてもそれは過去の結果です。
年は取るし、当然自分は変わります。世の中も変わります。今現在と同じなんて続くわけはありません。でもそれにさえ胡坐をすぐかくのが人です。
劇でのラスト、覚悟を決めた元帥夫人の姿は目に焼き付けておかなければなりません。そして夫人に諭されたオクタヴィアンとゾフィーは目を覚ますでしょうか?
二人にとって、こんな機会は二度ありません。
これも私自身が忘れてしまう、実に大切な教訓でした。
【いもたつLife】
PERFECT DAYS 2023日/独 ヴィム・ヴェンダース

主人公の平山(役所浩司)にあまりにも共感します。そして、その日常は私が描こうとしているモノにとても近いです。
早朝、向かいの寺の掃き掃除の音で目覚めて、極めて几帳面に身なりを整えて仕事にいく平山、その仕事は誰もやりたがらない公共トイレの掃除です。それを一生懸命に磨く平山。
昼休みもいつも同じ、公園にいき木漏れ日を撮影、時に苗木があるとそれを持ち帰り大事に育てます。銭湯が開く時刻にいき一番風呂を浴び、昭和の頃から続く駅地下の一杯飲み屋で酒と食事も毎日のこと。帰宅すると寝るまで読書を楽しみます。もう一つ平山の趣味は古い曲を当時のカセットテープで楽しむことです。
休日は部屋の掃除と洗濯、映した写真の現像、古本屋で次に読む本を選び、歌が上手いママ(石川さゆり)の店の常連客で、いつもより少し贅沢な酒盛りをします。
淡々とした毎日ですが、時に波風が起こります。同僚(柄本時生)のイザコザに巻き込まれたり、トイレで幼児の迷子に出会ったり、同じくトイレで見知らぬ人と五目並べをしたり、そしてもっと大きなイザコザは、何年もあったことがない姪っ子ニコ(中野有紗)が家出してきて数日一緒に過ごすのです。(ここで彼の過去が垣間見れます、裕福な家庭で育ち、親と折り合いがつかなく、底辺に近い今の仕事と生活は、彼が望んだことだと)
平山は他人と程よい距離を置きます。でもその人柄の良さは滲み出ていますから、皆から好かれます。(先頭の番台や常連客、居酒屋の店主、古本屋の店主、歌が上手いママ、よく合うホームレス(田中泯)(言葉を交わさないが昼休みの公園のOLとも心が通じている)等々)
平山は損得ばかりを追いません。トイレ掃除もそこまでやるかという気持ちが込められています。充実した日常を過ごすことで充実を得ることに満足をしています。
けれどこれがいつまでも続くとも思っていません。でも続けることに精進します。
ほとんど無口な平山が、ニコの前では彼なりに饒舌になります。そしてニコを迎えに来た何年もあっていない妹(麻生祐未)に親の死が近いことを告げられると、合いにはいかないと頑なですが涙を流します。平山も聖人君主ではなく人の子なのです。
ごくごく限られた人だけと触れ合い、親族ともほぼ交信しない、けれど、これまで生きてきた情があります。この生き様にもすごく共感します。
物語はお伽話のようでもあります。それは映画で語りたいことを優先したからです。とても良い映画でした。
そして、カメラ、ロケーション、キャスティングに唸らされました。
【いもたつLife】
【猿若祭二月大歌舞伎】

*新版歌祭文 野崎村
*釣女
*籠釣瓶花街酔醒
世話物、狂言、世話物と名作の間に一息つくプログラムでした。
釣女は落語好きにはたまりません。大笑いと苦笑いです。
野崎村は余韻溢れる演出でした。お光の純真な心の清らかさには大きな代償があり、それが久松とお染に伝わるかは最後までわかりません。もちろん伝わってはいるのですが、そのお光の気持ちが適うかは別です。そして、久松、お染、お光、人の心はどうしようもない、その心のままでは不幸になるけれど、他の道はあり得ないのです。性というか定めです。
その人の性を業とすると、籠釣瓶花街酔醒の次郎左衛門は花魁の八つ橋に翻弄されたとはいえ業そのものに支配されてしまいました。それだけ八つ橋を想っていたし、これまでの人生すべてを八つ橋にかけて幸せを手にできる一歩手前での八つ橋からの仕打ちは、次郎左衛門にとって死を掛けるほどの仕打ちだった、そこにたまたま名刀“籠釣瓶”が次郎左衛門の下にあったからの悲劇です。もし籠鶴瓶がなかったら起きなかった悲劇であり、人には宿命があるのではないかと思わずにはいられません。
三演目ともに堪能しました。
【いもたつLife】