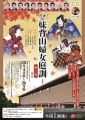いもたつLife
【spac演劇】伊豆の踊子 多々良淳之介 演出

演劇と映画とダンスが融合された楽しい演出の「伊豆の踊子」でした。
「観光演劇」と銘打たれているのが頷ける、映像には伊豆の名所が写り、ラストは原作の書生と旅芸人達と他の登場人物が現世に現れて伊豆観光を満喫している舞台とでした。
劇は、書生と踊り子たち旅芸人の旅(伊豆の映像付き)・宿でのひと時(これも映像付き)を順に追います。そして芸人たちの仕事、芸の舞台では、当時の芸の再現あり、歌あり、現代のダンス、パフォーマンスあり、そしてそれに合わせて映像(とミラーボール)を駆使して、時に観客を巻き込んで楽しませてくれます。
実直な書生と可憐で健気な踊子、そして踊り子の兄や義姉や母たちも真面目で、身分違いを超えての交流の様はとても爽やかです(役作りが上手い)。
書生はこの伊豆の旅の数日間、踊子との淡い純愛とこの一座との触れ合いが、これまでの自分を肯定させる貴重な体験になりその後の人生の転機にもなり、人生の大きな財産にもなります。
こういう体験は自分を振り返ってもあります。子供の頃、中学高校の頃、社会に出て間もない頃、いっぱしの社会人になってもその体験があるとないとでは大違いということ。
それらを心の中で再現させてくれました。
それは今の自分を作るとても大切なことで、書生と同じく今までを肯定させてくれることです。
その感覚はとても暖かく、それを導いてくれる劇でした。
最初のクレジットで豪華キャストに驚き、それらの人がちょい役で続々登場します。一度見では把握しきれませんでした。
その宝さがし感も良かったです。
【いもたつLife】
【国立劇場歌舞伎 妹背山婦女庭訓 <第二部>】
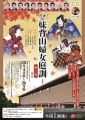
開館から57年でお役目御免の国立劇場(と国立演芸場)の千秋楽公演に立ち会えました。
10年程前に初めて文楽をここで観て、演芸場には何度か落語で足を運び、歌舞伎は昨年からの「初代国立劇場さよなら公演」にできるだけ通いました。
古びてきていますが、頑丈な建物はまだ現役でも十分と思わせますが、新しく建て替える国立劇場の構想を聞くと、ホテルやレストランの併設等、利便は当然良くなるので、2029年の再開は楽しみです。
さて、最後の通し狂言「妹背山婦女庭訓」は、飛鳥時代の大化の改新が題材ですが、舞台や衣装、登場人物の思想や人生観は江戸時代に焼き直されています。
歌舞伎はそういう柔軟性があるところが時代を超えて受け継がれていること、人気を博していることが窺えます。
蘇我入鹿の謀反を阻止しようとする、藤原淡海に命懸けで手を貸す二人の女、一人は町人、一人は入鹿の妹姫、二人の一途さとそれを受け止める淡海。これはこの演目の当時の価値観です。
また鎌足の家臣鱶七の格好良さと強さ、それに対する入鹿の家臣のあれやこれやも見どころです。
また入鹿が強かで、しかも超能力者という設定も面白いです。その超能力を奪う術などは、多くのSF漫画に影響しています。
そんな楽しい芝居の最後に、舞台挨拶です。もちろんこの劇場に対しての主催者、役者、観客皆の感謝になります。立ち合えてよかったです。
【いもたつLife】
【遠州横須賀街道ちっちゃな文化展】

掛川市の横須賀地区で開催された「ちっちゃな文化展」は、近代化されていない町並みを活かした町全体を芸術に仕立てた3日間のイベントでした。
町の家を間借りした芸術家のお披露目あり、街にいる芸術家の展示有り、街の人々の素人展示や、お祭りとして盛り上げる人たちと、ここぞとばかりに集った面々が作り出すアート体験場になっていました。
芸術家たちの作品ももちろん素晴らしいモノが多く、町の人が観光客をもてなす心も溢れてます。もう23回目ということもあり、街の人々が楽しんでしまおうという、それも無理しないでという大げさではない楽しみ方も気に入りました。
人口減で多くの転換を迎えている地方において、また、最近、芸術を身近に体感できる催しが増えてきている中、これをプロデュースした人は先見の明があると、それにも感心でした。
【いもたつLife】
【焼津 小泉八雲記念館】

お隣の焼津に、こんな立派な記念館があるとは知りませんでした。
そして小泉八雲が焼津とこんなにも所縁があることも初めて知りました。
丁度、松江の小泉八雲記念館(他の国の記念館も)との持ち回りの版画の展示もあり小泉八雲の、今でも、そして世界的に影響を与えた偉人ということも実感しました。
そんなに広くはありませんが、常設展だけでも見ごたえがある記念館でした。
【いもたつLife】
【藤枝市郷土資料館 昭和レトロモダン展】

昭和生まれの昭和育ちですから、懐かしいものばかりでした。
展示物が豊富で、知らないモノもあり、よくこれだけ沢山のグッズを揃えたものだと感心です、特に目を引いたのは、高度経済成長期後期を再現した家庭です。
「居間」「台所」「応接間」「子供部屋」はも~う、いかにもでした。
しかしこれを観て感じたのは、私たちは最大公約数の価値観を持つように常に洗脳されているのだということ。世の中は時代に関わらずそれが重力だと痛感しました。
【いもたつLife】
【グランシップ 本と音楽の素敵な出会い『ラブカは静かに弓を持つ』】

このイベントは作家の安壇美緒さんの「ラブカは静かに弓を持つ」がベストセラーとなり、その内容から、安壇さんのトークとチェロの演奏が組まれた訳ですが、チェロの演奏に圧倒されました。
もちろんナビゲーターの浦久俊彦氏が聞き手となった安壇さんの話も、
チェリストの横坂源さんとのクロストークも良かったのですが、チェロのソロ、ピアノとの演奏がもう感動モノでした。
ピアニスト沼沢淑音さんのピアノの伴奏も素晴らしいのですが、あくまでチェロを活かす伴奏で、主役は横坂源さんのチェロです。
曲目も多数で多ジャンルだったこともあり、チェロがこんなにも万能で、チェロだけですべての曲が網羅できること、ピアノが加われば無敵を感じました。
17世紀の名器のチェロだったことに加えて横坂さんの腕は超一流であることが(ピアノの沼沢さんも)、素人でもわかる演奏でした。
感動と共に、演奏に終始驚きという時間でした。
この企画を開催したクランシップに感謝です。
【いもたつLife】
夜の芹沢圭介美術館

「光の館 ヒカリノヤカタ 2023 夜の芹沢圭介美術館」と題し、
解放された一夜限りの贅沢な鑑賞でした。
企画展示は「のれん」。そして圭介の収集品。それらも見ごたえがありましたが、ライトアップされた美術館自体や庭園が幻想的で美しく、美術館を出た時は下界に戻ったような感覚でした。
夜の動物園も、夜の美術館も、そのものが持っている違う価値を見出す企画です。
【いもたつLife】
中勘助文学記念館

静岡市の郊外にあるので資料にある当時そのままに
勘助が閑静なこの地で生活していた様子が偲ばれます。
母屋は旧家の面影そのままで、私も子供の頃頻繁に訪れた祖母の実家を想いだしました。
勘助が実際に住んでいた庵もすぐにでも使えるままになっています。
とても綺麗に清掃、整備されていて心が洗われました。
【いもたつLife】
【グランシップ文楽 2023】

秋の恒例観劇になりました。文楽2本に、間にレクチャーがあり今年は呈茶のサービスもありました。
【昼の部】 義経千本桜 ~椎の木の段~すしやの段
この有名な演目は、昨年歌舞伎で通しで観ていたのですんなり入れます。
やはり文楽は巧みな人形の動きも注視しますが、義太夫の語りとの(もちろん三味線も)相乗効果の見応えがあります。
今回は前から二列目だったのでそれを堪能できました。
【夜の部】 桂川連理柵 ~六角堂の段~帯屋の段~道行朧の桂川
時代物も、人と人の妙が織りなす生きる誇りや儚さがありますが、世話物は、この演目は特に人の業と情けに胸を撃たれます。
義太夫節がこれでもかと攻めてきます。
主人公もどちらかと言えばダメで、周りにも主人公からかすめ取る嫌な輩、義母や義弟がいて同情出来かねる設定ですが、その主人公を愛する、また家を大事に知る妻や父がやっぱりいるのです。
でも主人子が選んだ道は。
普遍な物語でした。
今回の観劇で文楽の本当の良さが朧気ながら感じてきた感じです。
【いもたつLife】
ロスト・キング 500年越しの運命 2022英 スティーヴン・フリアーズ

2012年に一介の主婦フィリッパ(ハリー・ホーキンス)が行方不明だったリチャード3世の遺骨を発見した実話の映画化です。
あのシェークスピアのおかげですっかり悪者扱いのリチャード3世の汚名を晴らしたいフィリッパの情熱勝ちですが、そのフィリッパもリチャード3世の500年とは言わずとも、権力関係で日の目を見るまでには時間が掛かったことが最終版に描かれます。
フィリッパもリチャード3世も共にちゃんとと英国王室から認められて安堵です。
世間体、力関係等々で社会は動いてて、その力は強大です。
それを覆したのがフィリッパの何よりの功績だと思えてならない映画でした。
【いもたつLife】