- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2018年01月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年07月
- 2017年06月
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
ポテチ 2012日 中村義洋
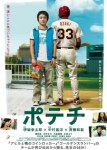
あるきっかけで母親を想って、母親孝行する主人公、
その訳は、主人公の劣等感と純粋な気持ちでした。
主人公はコソ泥、でも憎めないキャラクターで、
根も優しいし、真面目、正義感もあるのかあろうとしようとしているのかです。
その主人公と生年月日が同じ人物がいて、彼は主人公にとってのヒーローです。
ここが物語のキーです。
劣等感を持っていない人はいません。
そして誰もが親を慕っています。
でもその気持ちはちょっと隠れたところにあるものです。
主人公はそれをある出来事から目の当たりにすることになりました。
その瞬間から、自分は母親(物語の設定で父親は亡くなっている)
に何ができるかと、自分の存在は母にとってふさわしいかを考えることになります。
この物語はハッピーエンドです。
観客は良かったと、主人公も彼に纏わる人たちも、
次に進む道を見つけました。
でも主人公は、これから母に対してどういう息子でいれば良いかはわからないままです。
一時的に吹っ切れただけと心配しています。
しかし、新しいスタートができたことも事実です。
“そこは大事”です。
人生の中で区切りをつけることがやってくることは幸せなことです。
それを想わせる映画です。
余談ですが、
コンパクトにまとまっていて、無駄ない、テンポが良い映画でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
ニーチェの馬 2011洪/仏/瑞/独 タル・ベーラ

人類の破滅に向かう6日間を、父娘の生活で語ります。
そこには、人が死ぬまで生きる日常と、
絶望であっても日常を営むしかないのが人という生き物そのものを示し、
その生きる様の崇高さを朴訥に現しています。
映画は終始、モノクロの太陽が陰っている画、
世界の終わりをイメージさせる強風の、音と風景です。
唯一終わりが訪れた時のみ静淑になりますが、
その時は太陽は陰りではなく、現れません。
父娘の6日間は絶望(絶命)に進む道です。
しかも父娘は抗う術を講じ得なく、時が刻まれます。
途中、二人以外の人物が登場しますが、
それは破滅を告げる者と破滅を後押しする者の象徴です。
でも父娘は自分の日常において、自己の責任で生きることを主張します。
世界が破滅しなくても、死に行くことが宿命なのが人ですから、
日常を生きるのが生の全うです。
でもこの物語は、人が必死に生きるために確保したものを、
父娘から次々を奪っていきます。
それでも父娘は日常を続けようとします。
そこには絶望の中の生き様の崇高さを語っています。
そして、同じように日々を過ごす中で、
日々はいつもほんの少しずつ変わっていくこと、
それは老いであり、別れであり、失うことであり、できなくなっていくことです。
それを積極的に受け入れることが生きる義務ということを語っている映画です。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
風にそよぐ草 2009仏/伊 アラン・レネ

初老の男、妻子と孫までいる男が、財布を拾います。
そしてあったこともない、財布の持ち主に恋します。
男は失業者で、社会からあてにされていない存在です。
そして、妻も何故か醒めています。
ちょっと情緒不安定な男で、
財布の持ち主の女は、挙動不審な男を最初は受け入れられません。
けれどいつしか女は男が気になって。
という展開です。
女は小型飛行機乗りで、
男は飛行機に憧れていました。
この接点が映画のポイントになっています。
恋する男と、恋された女、男の妻、男の女友達の
不思議な関係の描写で、それぞれの心の底にあるものを醸し出している
そんな物語です。
成熟した社会で、役割を全うできなかった男と
役割を全うしている女達のギクシャクした関係を幻想的に現した映画です。
男と女の恋に共感はしませんが、
不満ではない今の生活に不安があるという現代の現実、
そこに惹かれる物語でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
【試写会】くちづけ 2013日 堤幸彦

まだ公開前なのでネタばれなしで。
知的障害者の社会的地位に言及している物語です。
当事者以外は誰も望まない最後を迎えます。
究極の選択でした。
何故こうなるのかを考えてしまう時点で、
障害者のこと、それを取り巻く環境のことが、
体感できていないのです。
綺麗ごとで差別しない。区別しない。
としているだけです。
じゃあどうするのという問いにも答えられません。
でもこの物語は、たまたま障害者を題材にしただけでしょう。
いつも起きている知らない実体は他にも一杯あります。
知ろうとしないではなくて、
綺麗ごとで知ってしまった感が満たされてしまう
情報が多いことが仇と思うことがよくあります。
だからこの物語の創り手も、工夫を重ねます。
琴線を刺激するために上質のエンターテインメントに仕立てます。
知ることでは何も起きないということはないはずだからです。
この試写会では、
主演、演出、脚本の宅間孝行さんの舞台挨拶がありました。
「少しでも良いと思ったら口コミしてください」
というメッセージでした。
そしてこの題材のきっかけの事件があり、
その事件は誰にも見向きもされない扱いだったとお話されていました。
笑いもあり、感動もあり、深く考えることができた映画です。
障害者のこと、その焼き写しの社会構図のことも、
多くを知ることができる映画です。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
アフロ田中 2012日 松居大悟

もてない男が彼女つくりに奔走する、
そこへ高校時代の悪友達が絡む、
上手く行きそうでいかない、
というベタな展開です。
主人公は25歳位の設定で、いまだ彼女なしの童貞男です。
この時点で世渡り下手というキャラが窺えます。
その純情な劣等生の不器用男の妄想と空想と、
おもいきれない性格と行動を描きます。
自己認定している独り言が気が利いていて、
上手い演出です。
苦笑いしながら、懐かしく共感しました。
大抵の男は(若い頃)自信がなくて、でも夢見がちの阿呆です。
もてない男にしては格好良いのが気になる主人公でしたが、
上手く演じていたし、演出も好感です。
そして、高校時代のおバカな、でも愛おしい仲間たちとの
やりとりにも懐かしく共感です。
主人公は、めちゃ可愛い彼女に好かれます。
ちょっと現実離れですが、
格好良い方が彼女との釣り合いはとれていましたからよしとします。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
ミッドナイト・イン・パリ 2011西/米 ウディ・アレン

1920年代のパリへ主人公がタイムスリップします。
そこには当時活躍中の芸術家達がワイワイガヤガヤやっている世界です。
主人公は自身にとっての憧れの時代・空間に夜な夜な通います。
夜中の12時にクラシックのプジョーが現れ、そこがタイムトラベルの入り口です。
粋な設定で、多くの人が迷いこみたくなります。
ウディ・アレン監督らしい、会話劇が、昼間も夜も続きます。
ただその内容が、教養ひけらかしの皮肉と、
真の文化人の会話という対比ですが、
どちらも毒ありで、アレン監督らしいところです。
パリ(当時でも今でもどちらでも良い)が好きなことと、
当時の芸術家達に思い入れがある程楽しめる映画ということは間違いないのですが、
それよりもウディ・アレン作品が好きかどうかの方が好きかどうかの決め手でしょう。
主人公は、1920年代のパリに憧れ、
1920年代の女性は19世紀後半の彼女が生きる前のパリに憧れ、
19世紀後半のパリはルネッサンス時代に憧れているという入れ子のくだりがあります。
きっと自分がタイムスリップできるとしたら、
それは自由自在ではないんだと、妙に納得したくだりです。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
道 白磁の人 2012日 高橋伴明

朝鮮併合後に韓国に渡り、
決して解り合えない民族間の根深い対立に抗した
浅川巧という人物の半生を描いています。
彼の素晴らしいところは、
小さな力しかない一個人が出来ることを
エゴでなく、それが自分の生きる道としていたことです。
彼も対立する民族が解り合えないことなんて重々承知でした。
真の友となった朝鮮人とも本当には心が通じていない、
それを受け止めるシーンは印象的です。
支配と被支配の両者の架け橋となったというのは歴史の後からの評価です。
彼はそれを目指していたわけではないでしょう。
今もそうですが、
価値観の無理やりな押し付けがあった時代です。
その環境下で「どうして?」という、人として受け止められないことを、
受け止められないとしていました。
魂の声を聞き、自分の生き方を自分で正す。
それができているかを振り返る人物像でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
神弓 2011韓 キム・ハンミン

映画中のほとんどが決戦という娯楽映画です。
大軍を相手に少数がゲリラ戦に持ち込んで、
人質救出と相手軍の壊滅をします。
王道です。
時代は1600年代ということで、
主要武器は弓矢。
それを駆使しての決闘です。
スピード感もあり、あっという間という印象です。
たまにはこういう映画も良いかなという感想です。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
にあんちゃん 1959日 今村昌平

極貧の四兄弟が食うことはおろか、
住むところも追われ、離れ離れで暮らすしかない。
けれど、なんと逞しく生きて行こうとするか。
という、勇気と、甘えを吹き飛ばせの、
メッセージ満載の映画です。
昭和28年頃、炭鉱町は閉山となる時代。
この兄弟は親を亡くし、長男・長女は働くが、
職を追われ、無い無い尽くしになり離れ離れに。
炭鉱町が役割を終えた様子もふくめ、
在日朝鮮人の差別や、彼等の結束、
また、まわりの人達の良心と、
食うことに困る本音、
それらを、訥々と造り手が感情を入れずに映すから、
受け手は素直に四兄弟(特に下二人の兄妹)が生き抜く姿に
見入ります。
炭鉱から、いの一番に追われた長男も
最後まで残った労働者もほんの少しの時間差で、
斜陽産業のあおりを受けます。
移ろう社会の姿、当時の激しい変化は、今に通じます。
人生は短いですが、その間多くの出来事にぶつかります。
今が良いとしたら、運がよかったのと、
今が良いといううちに準備は不可欠です。
この映画は感動させようとしてつくられていません。
だから、
この時代を生き抜いて来た人達も、
今の裕福な日本しか体験していない人達も、
あの時代の日本を(懐かしく)冷静に見つめることができます。
この映画も多くの人に観て貰いたい一本です。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
その夜の侍 2012日 赤堀雅秋
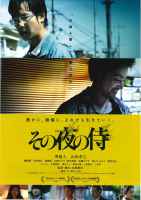
ある夏の日の3日間、
5年前にひき逃げで妻を殺された主人公が、
出所して、ノウノウと悪のままのさばっている男に復讐する、
というのが骨子ですが、
両者を取り巻く人間とのつながりがテーマです。
限られた時間の中で限られた人との中で生きるのが人生です。
もちろん誰と何をするかは自分が決めていることですが、
それを自覚していることはあまりありません。
ただなんとなく過ごしている。
不本意な奴と一緒にいることも、
また今日も不本意な一日であったとしても、
それはそれで仕方ないとしている。
ということを肯定も否定もしないで浮き上がらせています。
妻を失う=生きる価値を失う主人公、
支えは復讐で、それを想うことで生きている自覚を得ます。
それに対して、やりたいことを持たない、
気に入らないことが降ってくると、それに悪意で反応することで
生きる自覚を得る男。
そんな二人と関わりあう人達も、
二人をダシにして自分が生きている実感を得ようとしています。
それが無自覚であっても。
登場人物は皆、孤独ではいられないという選択をします。
生きることを崇高な観点からではなく、
泥臭い日常から見つめていく映画です。
ひとつ不満です。
この映画の設定の各所に現実感をそぐ部分があったことが気になりました。
私の主観ですが、惜しいと感じたので、一言。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】

