- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2018年01月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年07月
- 2017年06月
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
怒りの荒野 1967伊/独 トニーノ・ヴァレリ
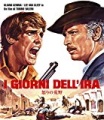
師弟対決もので、師匠のあまりの行為に、弟子が耐え切れなくなるという話です。
師匠タルビー(リー・ヴァン・クリーフ)はもちろん凄腕、正当防衛ではありますが、
殺しは厭わないし、それを誘いますから一応合法ですが、
目に余ることをしたことから、弟子のスコット(ジュリアーノ・ジェンマ)と、
ラストで対決になります。
スコットは父親が解らない娼婦の子ということで、街ではくみ取り等の下働きで、
いつか見返してやりたいという生活でした。
そこでタルビーと出会い、鍛えて貰う。
恩あるタルビーには従順だったのですが、スコットが譲れない行為をタルビーはしてしまった。ということです。傲慢は身を滅ぼします。
下働きのスコットはいかにも落ちこぼれ、それが、鍛えられて町に戻ると、鼻高々の嫌な奴、そして最後は師匠を倒す、この時は一人の男気ある人物に。
このあたりのメリハリが良かったです。
でもそのスコットが町の英雄にはならないところが、マカロニウェスタンらしいです。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
はなればなれに 1964仏 ジャン・リュック・ゴダール

こんな生き方していたか、しようとしていたよな、と実感してしまいます。
疾走感と虚無感がたまりません。そして刹那です。
どう生きるのかわからない若者像ですが、それは年を重ねても同じです。
でも若者はそれを付き詰めようとします。かなり乱暴に。
でもそんな雰囲気を喜劇で見せきってくれた、そんなゴダール作品でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
ラン・ローラ・ラン 1996独 トム・ティクヴァ

ローラ(フランカ・ボテンテ)は恋人マニ(モーリッツ・ブライブトロイ)の尻拭いのために20分で10万マルクを調達しなくてはなりません。
そのために、さあ走る走る、これが3回トライされます。
ローラの父親は銀行の頭取らしく、それをあてに走る走る、
でも1回目はあえなく失敗、2回目は微妙に好転しますが、ダメ、3度目の正直でという物語です。
ローラの3回のトライは微妙に違ってきます。
その微妙な違いは、大きな違いという結果になります。
これはローラとマニの運命が大きく違うだけでなく、走るローラをほんの少し触れ合う人達の人生も大きく変ります。
これが面白い。
冒頭、哲学的なメッセージで始まり、劇中にそれを表現しているようです。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
乳母車 1956日 田坂具隆

本来ならひとつを選べば、ひとつは諦めなければならないのに、
ずるい大人は、両方手に入れようとします。
でもそれは単にずるいだけか?
多感な女子大生ゆみ子(芦川いずみ)は、そんな父 桑原次郎(宇野重吉)の一面を知り悩みます。
桑原家はブルジョワです。ゆみ子、次郎と母 たま子(山根寿子)の3人家族で、お手伝いさんが二人です。それは次郎が会社役員だからです。
おっとり優しい父に25歳の愛人がいることを知ったゆみ子は、たま子にそのことを告げると、たま子はとっくに知っていて、黙認していることを知り、たま子にも不信を持ちます。なあなあでいることで、母は今の贅沢な生活ができること、騒ぎ立てない方が次郎を苦しめることになるという、たま子の生きる選択に、それが本当の生き方かと疑問を持ちます。
どうしても愛人のとも子(新珠三千代)に合わずにはいられないゆみ子です。
意を決して合ってみると、とも子は礼儀正しく、芯が強く、美しい女性ということで、嫌悪感を持てません。そして、とも子には一見ぶっきらぼうですが、心根は優しく気概がある弟の宗雄(石原裕次郎)がいて、宗雄は姉を慕っていて、彼の好青年ぶりからも、この姉弟に少し惹かれます。
そして、とも子には赤ん坊のまり子がいて、この母違いの妹がとても可愛くなってしまいます。それは宗雄も同じです。
次郎、とも子、たま子は皆、ぬるま湯のような現在の境遇に、それは実はただの時間稼ぎなことを心で隠して、満足を得ようとしていましたが、ゆみ子のたま子に対する意見が、それは上辺だけの生き方だという警鐘となり、その関係を見直すことになります。
たま子は家を出る事で、ゆみ子は今の生活を、次郎からの、お手伝いさん付きの家と生活費を貰う生活に甘んじることは、精神的にできなくなるのです。
次郎と別れて自活を試みるとも子ですが、ここで厄介な問題になったのが、まり子の境遇です。
まだ生後半年なのに、母と一緒にいられる時間が限りなく少なくなってしまい、それを許せないのが、ゆみ子と宗雄です。
二人は、大人3人に、まり子の生活を一番に考えて欲しいと直談判します。
次郎はもちろん今の社会的地位も若く美しい愛人も、そして生まれた可愛いまり子も全部を得ようとしています。そんなことはあり得ないのに。
たま子も重役夫人の生活をしながら、次郎に罪悪感を感じて貰うことで、自分の心の奥にある許せない気持ちを抑えています。これも長く続くわけはありません。
とも子も、愛する次郎に守って貰い、もちろんまり子とは何不自由ない生活をしながら、でも桑原家は安泰(たま子もゆみ子も今までの気持ち=次郎を慕って仲良い家族のまま)で、いて欲しいという、これまたあり得ない現実を望みます。
この状態が続くわけはなく、3年は直面することになります。
直面とは、社会のルールにです。
やはり社会は許してくれないのです。
ただ、その社会のルールとはでは何か?を考えさせられます。
そのルールとは、大多数の人が生きやすいように、また為政者がやりやすいようにしてできたシステムが社会のルールです。
人の感情や本能から導きだされたモノではありません。
ここが厄介です。
次郎がとも子を好きになり、とも子も同じ気持ちになり、子供ができる。そしてその子を溺愛する。これは本能で、いかんともしがたく沸きあがってきた心の叫びの結果ですが、社会のルールはそれを許しません。
たま子の生き方だっていいではないですか。
でも三人三様に罪悪感を持ち、ゆみ子と宗雄は嫌悪感を持ってしまいます。
もちろん不倫が良いこととは思いませんし、次郎ととも子の関係で、多くの人(家族)が傷つきました。
けれど、それぞれの人が持つ、罪悪感や嫌悪感は社会が作りだしてしまったものではないとは言い切れない、それを強く感じました。(本編で次郎もそれを吐露しています)
人らしさとは、適合して生きる事なのか、自分の気持ちを偽らないことなのか。
でも次郎ととも子の恋愛はやっぱり軽率ですが。
また、たま子が家を出る、とも子が自活するという背景として、女性の自立が大きなテーマにもなっていました。
これは、昭和31年という、日本が勢いを持ち始めたことがガンガン伝わってくる映像と共に映画の中に封じ込められていました。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
ある戦慄 1967米 ラリー・ピアース
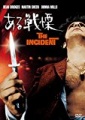
嫌らしい見応えがある映画でした。
途中、もうこんなシーンは長すぎる、もう終いにしろと言いたくなります。
それほど、見たくないものを見せます。
それは、個々人が持つ、触れたくない心を赤裸々にするからです。
日曜深夜のニューヨークの地下鉄に乗り合わせた乗客がその一車両の中で、二人のチンピラに絡まれるという設定なのですが、これが見事に、チンピラ二人を含めて、乗客たちの生き様を人には見せたくない心が抉り出されるのです。
チンピラ二人(トニー・ムサンテ、マーティン・シーン)はかなりの悪、そして二人が地下鉄に乗るまで訳有りの人達がその車両に乗り合わせます。
妻の実家で娘の誕生日祝いで過剰なサービスを受け不満を持っている夫の3人家族。
熱々でイチャイチャしている若いカップル。
息子に借金を断られ、だから最近の若い者はダメとばかりに不平を言う老人とその妻。
休暇中の若い軍人二人、一人はエリートで弁護士志望、もう一人は怪我もちで田舎から出てきた軍人。
冴えない高校教師とその夫を甲斐性無しと罵る妻。
アル中をなんとか克服しようとしている初老の男と、その後をついてきたゲイの青年。
白人を嫌悪している黒人男性と、そこまで毛嫌いしても良いことはないと、いつも男を治めている妻。
映画は冒頭チンピラ二人の悪ぶりを映し、その後の前半で、登場人物達の人となりを手早く丁寧に映します。
そして後半は乗客の車両にチンピラが乗り合わせて、イジメが始まります。帰途の駅まで我慢して乗っている乗客たちですが、途中からチンピラがドアを開かないようにして密室劇になっていきます。
ゲイの青年を手始めに、次々とイジメをしていくチンピラ二人、止めに入る男もいますが、逆に虐げられるという構図繰り返され緊張感が増していきます。
この映画の面白いところは、チンピラが単に悪さをして、見て見ぬふりをする乗客というだけの関係に迫るのではなく、チンピラのちょっかいを通して、それぞれの関係ある夫婦(恋人)関係のその人物のこれまでを露にするところです。
お互いがお互いにわだかまりがあり部分がこういう極度の緊張状態になることで、隠せなくなる人の性が炙り出されるのです。
その嫌らしさは誰もが大なり小なり自己の中で感じていることであり、自分の生き様を問われているようで、見ていて不快になるのです。
100分と言う尺で見事にそれをまとめている脚本と、機微に至るまでの真実味あふれる人の態度をしっかりと演出している秀逸さです。
カメラもアップを多用し、構図も縦横無尽で、ワンシチュエーションでありながら、飽きさせません。
登場人物を通じて、差別問題、格差問題と都会にくすぶる諸問題を描いてもいます。
とても嫌らしい、良い映画でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
無防備都市 1945伊 ロベルト・ロッセリーニ

飢えているために、市民の間で争いあってしまう、市民がパン屋を襲撃するシーン。
テロ活動をしようとうするイタリアの少年。
逮捕され連れ去られる恋人を追いかけた女が銃殺されてしまう有名なシーン。
仲間を売らないがために、拷問で殺されてしまう男と、それをしてしまうドイツ兵。
生きるために恋人までも売ってしまった女
「俺たちは殺して殺して殺しまくった、それが憎悪を生んだ。俺たちは絶望の中で死ぬんだ」と語るドイツの高級将校。
拷問に耐えることができないことを悟り、口を割らないために自殺するイタリア兵。
「死ぬのは難しくない。生きるのが難しい」と処刑前に語る神父。
凜として殉教死に臨むその神父を撃ち殺すことができない、自国イタリア兵たち、それを見て撃ち殺すドイツ将校。
それらをしっかりと瞼に焼き付ける子供たち。
第二次戦争末期に同盟国だったドイツに占領されたローマで起きていた光景です。
平時では起こりえないことが起こる。人が狂気を持つ。
まだ熱いさなかに作られた戦争を記録したかのような映画です。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
ヒッチコック/トリュフォー 2015米/仏 ケント・ジョーンズ

書籍「映画術 ヒッチコック/トリュフォー」の断片を実際の映像で示し、またそれらに著名な映画監督の視点を加えて、また、書籍を作る際に行った実際のインタビューの音声(ヒッチコックとトリュフォー)を交えた、ヒッチコック解説映画です。
30以上の作品映像が映され、また、トリュフォーの作品もチラッと出てきます。両監督ファンのための映画ともいえます。
まだみた事がないヒッチコック映画も、見てきた映画も見たくなりました。
限られた時間ですから、鑑賞する映画は選ばなければと、改めて痛感もしました。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
南の島に雪が降る 1961日 久松静児
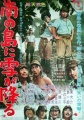
1943年西ニューギニア、マノクワリ、敵機に脅かされ、補給線は絶たれ、味方に見捨てられた兵士達、武器はもちろん食料もなく、飢えやマラリアで皆瀕死という中、希望を見出していくという、原作者の加東大介の実体験に基づいた映画です。
司令部の小林少佐(三橋達也)は、加藤軍曹(加東大介)が前進座の俳優ということを知り、兵士達を少しでも癒すことができるように、司令官(志村喬)の許可を得て、加藤に演劇部隊を作るように命じます。
全部隊から演劇関係者(俳優から脚本家、美術スタッフまで)を募り、稽古し披露すると、予想以上の大成功になります。
司令部も全面バックアップし、「マクノリア歌舞伎座」が立ち上がります。
絶望の中、娯楽がどれだけ生きる気力になるかが描かれます。そしてそのために物資がないけれど知恵を出し合い、努力も惜しまず、また期待されることに応える喜び、兵士達ももう多分戻れない内地を懐かしみます。
クライマックスはもう一度雪を見たいと事切れそうな兵士のために雪を降らせての「瞼の母」です。
反戦映画ですが、殺し合いや戦闘シーンはありません。全編人情喜劇です。
それはキャストからも想像できます。
伴淳三郎、西村晃、桂小金治、佐原健二、渥美清、三木のり平、有島一郎らの芸達者たちが生き生きと演じます。
そしてただの喜劇では終りません。
「日本は一度戦死と発表したら、決して取り消さない」などの言葉が挿入されたり、
一部の部隊はもう戻れない死の行進をしたり、マクノワリの中でも最も戦闘が激しく、瀕死揃いの部隊の現実も描かれています。
それらにも芸達者の、森繁久弥、フランキー堺、小林桂樹らがしっかり演じます。
当然高品質の演技合戦になります。
大量破壊兵器で多くの死者もだしましたが、ここでは戦闘よりも飢えや病気でなくなった人が多かったあの戦争の一面の真実を語ります。
脚色はされているでしょうけれど、実話に基づいています。
この戦場では絶望の中で人らしさを終戦までずっと与え与えられていた、娯楽にある、人に希望を与える力を物語ります。
そしてこの映画は、実際の戦争体験者がそろっていたからこその、あの出来栄えだともいえるでしょう。
追伸
12/21は「冬至」です。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「冬至」の直接ページはこちら
冬至
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
イレブン・ミニッツ 2015波/愛 イエジー・スコリモフスキ

午後5時からの11分間、市中でお他愛ないどこにでもありそうな出来事が、ある一点でどんでん返しでつながる群像劇です。
女優とその嫉妬深い夫、女優は映画監督の面接を受けます。映画監督は下心満載で、この出来事がラストのきっかけになります。
巻き込まれるのは、
出所したばかりの屋台の気前の良いホットドッグ屋の主人とその息子。息子は人妻と不倫関係のバイク便屋。
そのホットドッグ屋のお客の修道女たち。
映画の撮影現場に偶然居合わせた老画家。
部屋で男とポルノ映画を観る女、その男はビルの壁の修理屋。
質屋強盗を失敗した少年。
犬を元彼から返してもらって連れ歩く女。
救命隊員の女医と仲間、彼らが助けた産気づいた女とその家族
他にも居たかもしれません。
その市中の人達の11分間を細切れに映して、人となりを紹介し、
11分後の姿を最後に見せます。
出てくる人達の人となりは解りますが、掘り下げはしません。
あくまで観ている観客とそんな遠くはないということを言いたげです。
そして思いがけない出来事が起こる、そんな世の中を表現します。
9.11を匂わす映像や、訳がわからないことが起きていることを告げること、
ちょっと不思議な現象を挿入することから、
一寸先と繋がるはずがない者が繋がるという現代を謳っているようです。
感情移入をさせないで、それを描く、上手い造りの映画でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
イレブン・ミニッツ 2015波/愛 イエジー・スコリモフスキ

午後5時からの11分間、市中でお他愛ないどこにでもありそうな出来事が、ある一点でどんでん返しでつながる群像劇です。
女優とその嫉妬深い夫、女優は映画監督の面接を受けます。映画監督は下心満載で、この出来事がラストのきっかけになります。
巻き込まれるのは、
出所したばかりの屋台の気前の良いホットドッグ屋の主人とその息子。息子は人妻と不倫関係のバイク便屋。
そのホットドッグ屋のお客の修道女たち。
映画の撮影現場に偶然居合わせた老画家。
部屋で男とポルノ映画を観る女、その男はビルの壁の修理屋。
質屋強盗を失敗した少年。
犬を元彼から返してもらって連れ歩く女。
救命隊員の女医と仲間、彼らが助けた産気づいた女とその家族
他にも居たかもしれません。
その市中の人達の11分間を細切れに映して、人となりを紹介し、
11分後の姿を最後に見せます。
出てくる人達の人となりは解りますが、掘り下げはしません。
あくまで観ている観客とそんな遠くはないということを言いたげです。
そして思いがけない出来事が起こる、そんな世の中を表現します。
9.11を匂わす映像や、訳がわからないことが起きていることを告げること、
ちょっと不思議な現象を挿入することから、
一寸先と繋がるはずがない者が繋がるという現代を謳っているようです。
感情移入をさせないで、それを描く、上手い造りの映画でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】

