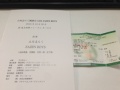- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2018年01月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年07月
- 2017年06月
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
【SPAC演劇】 黒蜥蜴 宮城聰 演出

【SPAC演劇】 黒蜥蜴 宮城聰 演出
三島由紀夫の死生観が匂う演劇でした。
死生観とは、どう自分は生きたかの結果が死で、その生き様の元になるのは人はどうやって誰に愛を与えるのかです。
黒蜥蜴は女としては生きていけない、黒蜥蜴としてしか生きられない女でした。
けれど情念の女でもありました。
人生でただ一度、明智の前で女としての喜びの一瞬がありました。
女として生きたのはあの時だけで、それが黒蜥蜴に死を選択させるのですが、彼女には死に値することだったのです。
私にはあの場面がこの演劇の最大の見せ場でした。
黒蜥蜴が明智を死に追いやることを決め、その死の目前に自分の愛の告白を明智にするシーンです。愛を告白することで黒蜥蜴は女になり、それだけでエクスタシーをも感じます。(このシーンはあの黒蜥蜴でさえも女の喜びを望むということを観る素晴らしいシーンでした)
明智を死に追いやることは明智への愛ですが、愛の告白を封印するのが黒蜥蜴としての生き方です。でも黒蜥蜴は女になり愛を告げてしまったのです。黒蜥蜴が女として生きた一瞬でした。
良い演劇を見せてもらいました。あの冷静沈着な明智までもが愛を求め、与える姿を通して、誰もが迎える死を考えさせてくれます。どうやって死を迎えるかの勇気は愛を与えることで得られるのかもしれないと強く感じました。
いい年になると死を身近に考えるようになります。どう死ぬかは、今からの短い人生をどう生きるかです。それはどういう愛し方をするかということをこの演劇で想います。
この演劇では貰う愛ではなく与える愛が描かれています。
明智は黒蜥蜴を捕らえることが彼女への愛情表現です。黒蜥蜴も日本一の探偵の明智の上を行くことが明智への愛情表現です。
黒蜥蜴を愛した雨宮は黒蜥蜴を振り向かせることができない男でした。そのチャンスを貰うために黒蜥蜴の奴隷になりました。でも黒蜥蜴を自分に振り向かせる機会を得ることとそれを実現することを虎視眈々と狙っていて、その機会が訪れると死と引き換えでも黒蜥蜴を振り向かせようとします。それさえあれば死は本望なのです。
もう一人死を覚悟する女がいます。黒蜥蜴に狙われた早苗の替え玉になった女です。彼女は自殺未遂をしました。だからもう死を怖れないとして、また高額な報酬もあり替え玉になります。そして黒蜥蜴に捕らえられ、雨宮と一緒に死までの秒読みに晒されます。
そんな状況で替え玉の女は雨宮のために死を喜んで引き受けます。女も愛を与えることで死を迎える覚悟をするのです。
この4人は死を厭わないのですが、これは特殊でしょうか、それに答えることは出来ませんが、少なくても私には、この世界は現実で身近でした。
当然のごとく、死をいつも考えている訳ではありません。それはこの演劇の登場人物達にもいます。事の発端になった宝石商の岩瀬と、黒蜥蜴に狙われた娘の早苗は死のことなど考えていません。その他の人、出てくる市井の人々も同じです。当たり前です。
私はこの演劇で何かを求めているから死をテーマに鑑賞します。だから死生観を訴えていることに呼応するのです。
そういう観点からも秀逸と感じました。黒蜥蜴はじめ、明智、雨宮、替え玉の女は死を直面して生きているという当たり前ではない姿ですが、凜とした生き様を見せてくれるからです。
この演劇は三幕構成です。一幕は黒蜥蜴が早苗を誘拐未遂に終わるまでです。明智と黒蜥蜴の第一回目の対決があり、大阪に来た岩瀬と早苗が黒蜥蜴の罠にかかり早苗が連れ去られますが、明智が用意周到なために早苗を取り戻し、ここで黒蜥蜴との対決が始まります。
同時に主要人物が登場しその人となりが露になります。そして、今後の物語の仕込みとなり、明智と黒蜥蜴が惹かれあうことを示し、最も注目するのはそれらの表現が三島由紀夫の死生観で、それを明智と黒蜥蜴が吐露していることです。この演劇の仕込みが出来上がります。
ここで休憩が入り、舞台も雰囲気も変わります。舞台は東京の岩瀬邸です。万全な警護の中で見事黒蜥蜴が配した手下が早苗の誘拐に成功します。
悔しがる明智ですが、ふと、どうしても早苗を取り戻したいのか岩瀬氏に尋ねるという場面もあります。どうも黒蜥蜴の思惑だけでは片付けられなくなることが雰囲気で匂うのです。
そのように、原作の面白さを元にしてあくまで明智と黒蜥蜴の内面に迫るのがこの演劇です。
第二幕はそこから黒蜥蜴が、岩瀬が早苗の次に大事にしている宝石「エジプトの星」をまんまと奪い取ることから、早苗が黒蜥蜴の本拠に運ばれる船へと進みます。
ここで黒蜥蜴は思いもよらぬことに遭遇します。誰にも付けられているはずがないのに明智が船に乗り込んでいることを知るのです。そして、その明智を葬る行為に移ります。黒蜥蜴として生きる当然の行為です。そして葬る寸前に前述したように黒蜥蜴は明智を愛する一人の女となるのです。
これは永遠の別れが成せる業がきっかけで女としての本性が表出したのです。
明智を葬ったとした黒蜥蜴は失意を隠し、いつもの黒蜥蜴に戻り演じます、装います。
そして第三幕へ、黒蜥蜴の隠れ家です。早苗を剥製にする、黒蜥蜴のコレクションに加える場面です。
ここで全ての愛の行方と、死への覚悟が決せられます。
まず雨宮が死を掛けて黒蜥蜴の嫉妬を誘います。今まで黒蜥蜴の奴隷でしかなかった雨宮は、一方的に黒蜥蜴を想うばかりで、一度も振り返らせることができませんでした。雨宮が死を掛けても黒蜥蜴に自分を振り返えさせることを実行したのです。
その相棒にされたのは、早苗の替え玉でした。彼女は世を捨てた自殺未遂の女で、明智の誘いで危険でも生きる術を与えられた女です。
その替え玉の女は雨宮を愛したのですが、替え玉でいることが雨宮の希望であると知り、替え玉でいることは死を選ぶことになりながらそれを選びます。
物語は黒蜥蜴の生き様が常に問いかけられますが、このサイドストーリーでもある雨宮と替え玉が死を望むことで深みが加わります。
雨宮は黒蜥蜴を愛していたが一度も黒蜥蜴から愛を受けられません。でも嫉妬させることができるだけで雨宮には満足なのです。黒蜥蜴は明智以外を愛することはない、もっと言えば人を愛することがない女のはずなのに、明智を愛してしまった、だから、奴隷扱いの雨宮に好意を持つなんて黒蜥蜴にはあり得ないことですが、雨宮はその黒蜥蜴を嫉妬させることが出来たのです。
その代償は替え玉の女の死です。この女も喜んで雨宮の喜びのために死を選びます。
しかし、物語は明智の一枚上の頭脳と行動力で解決に向かいます。
死に追いやったはずの明智が生きていたことを驚くと共に喜ぶ黒蜥蜴ですが、表面的には追い詰められます。逮捕という現実ですが、黒蜥蜴にはそんなことはどうでも良い事です。明智が生きていたことは、もう黒蜥蜴として生きていけない選択を迫られたのです。女として明智を愛したことを吐露した以上それを知った明智が生きていたのならば、当然、黒蜥蜴としてもうこの世にいられないということです。黒蜥蜴は「私は誰なのかかがもう曖昧になってしまう」ことになります。彼女は黒蜥蜴で生きることで私だったからです。
明智の前で死を選んだ黒蜥蜴ですが、黒蜥蜴を装っていてでも女となり、それを受け入れてくれた明智の前で死ぬことは本望だったように映ります。これは三島由紀夫の死に様と重なります。
でも最も感動したのは、明智の最後の言葉です。「宝石はもうなくなってしまった」
黒蜥蜴を失ったことで、黒蜥蜴に対する明智の本心が最後の最後の言葉でわかります。
明智は黒蜥蜴を追い込むことが愛の証で、それを黒蜥蜴も受け止めていました。でも黒蜥蜴はそれが本当に明智の愛なのかを悩んでいました。観る者も明智はどこまで黒蜥蜴を想っているのかに注目しています。それが最後にむき出しになったのです。
明智も黒蜥蜴を愛することはどちらかが死を迎えることだと覚悟していました。
そしてその通りに、もっと言えば明智が事件を解決することは黒蜥蜴の死が確実になることでしたが、それでしか報えることができないことを最後に嘆きました。
物語の中で明智の人間らしさをみました。
感動した演劇です。切ない愛がたくさん描かれていたからです。
それらは三島由紀夫の死生観でありそこに共感しました。そしてそれは、私達が死に向うにおいての現実として、見たくないけれど抱いている感覚だからでもあるからです。
原作も、ミステリーとして最後までどんでん返しがありといった設定で面白いから演劇として第一級と楽しめますし、第一幕からはちきれんばかりに満ちている三島由紀夫の生き方・考え方が台詞に込められているので、その大量の言葉を受け止める大変さと心地よさも感じていました。
そして、演劇としてそれを具現化して盛り上げてくれます。黒蜥蜴と明智の主演俳優二人の圧倒の演技はもちろん、息抜きのようなユーモアがあり、でも常に緊迫感がある舞台でした。音楽も、黒蜥蜴パートと明智パートで少しテンポと音階が違うことで、二人の心情を表現していました。
幕の繋ぎも自然だし、本当に完成されている演劇でした。
繰り返しますが、死を迎えるというテーマに対して、どう愛を表現するかは不可欠な一つだと思いました。
この黒蜥蜴と明智の愛の表現は特殊ですが、その根底にあるものは特殊ではありません。悔いなき死を迎えることには覚悟が必要だということ、どうやって私自身が持つことができるかが肝心なのです。それは黒蜥蜴と明智、二人は根底に持っていたことで、それを生き方に反映していました。
人の死というひとつの最大の難問に対する答えを示唆してくれたのだと痛感しています。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】青森県のせむし男 寺山修司作 渡辺敬彦演出

大正家の女中マツが恨みを晴らす、女の情念の話なので、暗くなりがちですが、敢えて部分的にコミカルな演出をしているように思いました。
私は寺山修司氏の「天井桟敷」の演劇はみたことはありませんが、この演劇も寺山氏への敬意が込められていることでしょう。
そして、演劇はそんなにかしこまらなくても、気軽にどうぞという雰囲気がありました。
会場に入るとお囃子のような音楽が聞こえてきます。
そして演出家の渡辺敬彦さんの挨拶や終演後の俳優紹介でも、俳優の皆さんのお見送りでも、それを感じました。
中身はコミカルな部分があるとはいえ、アングラ色満載でした。
女中であるが故に、若旦那に身籠らされてしまうマツ。世間体から入籍はされますが、女中扱いが30年続きます。
そして肝心の生まれてきた息子は、醜いせむし男で、育てることすら許されなかった運命だったのです。
そして、夫は早くに亡くなり、想像ですが、恨みつらみを一度も夫に吐露することが出来なかったのでしょう。そのアンフィニッシュな気持ちがマツの情念、世間に対しての恨みの原動力で、マツの復讐劇です。
おもいっきり日本っぽい演劇です。
太鼓と三味線、浪曲師のような語り部が話を進めます。
神社仏閣を思わせるセット、周りも竹やぶで、全体的に暗い舞台には時に満月が浮かびます。
時代も大正時代からはじまります。
マツの情念の凄さがわかるのは終盤で、外堀を埋めるように劇は始まり進みます。
大正家の二人の侍従が語り部のアプローチを受けて、その詳細を伝えます、時にコミカルに。
もう一人の侍従は大正家と話を締めるかのように、プロットにけじめをつけます。
そして三味線とともに語り部が話を進めるのですが、この語り部も物語の重要人物で、語り部から物語の人物へと移行します。
そして、死んだはずのマツの息子のせむし男が現れます。
だから段々と散乱していた、登場人物と、物語に無関係な人物が、収斂されて核心へと迫り、マツの想いをこちらに想像させる展開になります。
マツが主人公ですが、せむし男も同様です。
マツの心情は露呈されますが、せむし男の心情は匂わせるだけです。
そしてマツの心が明らかになると、せむし男がどうしてここにきたか、どうやって生きてきたかを注視します。
せむし男は、マツが産んだ息子かは明らかにされません。
私はどちらでもマツは同じ生き方をしたと思うからどちらでも良いのだと解釈しました。
どちらでもマツは非情な情念を持つ女になったのだと。
そして明らかに健気なせむし男は何故存在したのか?
これも非情の象徴だと思いました。賽が投げられた後では世界は変えられないと、ということです。
この演劇は、登場人物すべてが戸籍を失うことから始まります。
誰が誰とは特定できないということです。でも実社会では相互の関係で誰が誰かを認め合います。
これは社会の二面性です。
誰が誰とは確定できないけれど、でも“あいつに違いない”という存在は、人の悪意に対してはこれ以上ない存在です。
小さな悪意を産み、満たすのです。
その標的がせむし男だった。
それは劇中のカゴメの歌であきらかです。
そうすると想像以上に非情な物語です。
せむし男は、ただただ地味に生きたい。でも、世間とは違う“みてくれ”から世間に引っ張りだされます。
世間に抗することが出来なかったとともに、世間なしでは生きられないのです。
マツはそんな世間に復讐をする立場になりました。
せむし男はそんな世間から逃れられないで、巻き込まれました。
でも結果どちらも不幸にしかみえませんでした。
spacの若手俳優が中心になって立ち上げたのが本作というのを観劇前に知りました。
その俳優達はやはり芸達者で、細部も丁寧に造られていました。
勢いがある演劇と感じました。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】黒蜥蜴 江戸川乱歩原作 三島由紀夫作 宮城聰演出
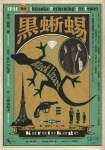
観劇後、もう一度観る事を決めました。面白かった、素晴らしかったです。
最後まで見ると揺ぎ無い愛の物語とわかりますが、演劇全体を通して感じるのはいかに生きるか、どう死ぬか、でもその死さえも通過儀礼であり、自分と言う存在の終わりではない。そんな死生観が貫かれています。
三幕構成で、一幕は黒蜥蜴と明智小五郎の出会いと、お互いを知る、お互いの心を探る、自分は互いに相手をどう思っているのかを探ります。それは長回しの台詞の応酬で、知的な会話、抽象的な言葉でこちらに訴えてきます。
恋にも発展していきますが、お互いを好敵手として捉えるところが重要です。
正義と悪、敵でありながら、お互いは自分を鍛える存在であり、この戦いこそが生きる術となることが仕込まれます。
ニ幕からは、スリリングな展開となり、トリックを使った化かし合いになっていきます。
そして空間が違えども、二人の掛け合いがあり、ここでも粋な台詞の応酬です。
三幕はよりサスペンスでよりテンポ良くなり場面も変わりますし、解決に向ってはいるのですが、二転三転する面白さです。
対決を楽しむ黒蜥蜴と明智で、三幕で明智を殺したと思い込んだ黒蜥蜴の悲哀から、実は生きていたことで、明智を愛することに対して、自分に問うところは圧巻です。
自分が愛していることを受け入れるのか、受け入れるとしたらどうするのか、その矛先が死であることを覚悟するという、愛情表現の仕方は黒蜥蜴の美学であり、生き方であり死に方でもあります。
これと同時に、黒蜥蜴を愛しながら愛されないことを悩む雨宮が、死を厭わない方法で黒蜥蜴を嫉妬させることに成功したときも、死生観が現れます。
進んで死を選ぶ、その価値観は戯曲の作者三島由紀夫の生き様でもありました。
物語としても面白い上に、三島由紀夫の美学が加えられた戯曲が、宮城演出で引き出されていたというのが、今回の印象で、でも、まだまだ観たりない、もっと観たいというのが、終わった時点の率直な気持ちでした。
セットも凝っているし、照明に映える衣装の黒蜥蜴も美しかったし、何より黒蜥蜴と明智の兵ぶりが良いのです。欲望溢れる中に、冷静で理知的でもある黒蜥蜴は女らしさも秘めています。たきいみきさんの代表作となるのではないでしょうか。
明智小五郎も沈着冷静で自信たっぷり、一見理路整然でしか動かないようでも、熱さも持っている、大高浩一さん流石です。成りきっていました。
もう一度、みることができるのが本当に楽しみです。
【いもたつLife】
立川談笑 独演会
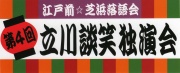
初代立川談笑の追悼の落語会が、浜松町の正伝寺の本堂で開催されました。
もちろん6代目の独演会です。
前座の笑坊さんの「寿限無」の後、仲入りなしで二席でした。
枕から大いに盛り上がり「金明竹」に入りました。
関西弁から津軽弁に変更しての一席で、師匠の得意ネタのようで、本家本元の青森でもとても受けたとのこと。
金明竹は大好きな落語で、私は三代目三遊亭金馬が最高と思っていましたが、それに匹敵でした。
そして「子別れ」です。
昭和30年代後半という設定の、師匠お得意の改作という感じ。
その時代設定を十二分に活かしての一席でした。
年代が同じことから、通じる背景も多く大満足で、オチも最高でした。
来年も談笑師匠は追っかけなければ、というのが感想です。
【いもたつLife】
柳家花緑 独演会
静岡市の駿府公園内にある、
茶室での“柳家花緑の落語会”が定期的に開催されます。
84名の定員、小さい箱での落語会で、なんと肉声で聞けるという贅沢な会。
今回も抽選であたり、席順は入金順ということで、なるべく早く振り込み、
9番目の席、前から二列目です。
高座とは2m位しか離れていません。
まずは、二つ目の花ん謝さんの「真田小僧の序」でした。
枕も上手で、落語も上手で、花緑師匠に繋ぎます。
そして「笠碁」。
生で観るのは初めてでしたが、見事な一席でした。
言葉ではなく、雰囲気で表現する芸で、音声では何度も聞いていますが、
この噺はやっぱり生でないと堪能できませんし、上手くないと満足できないのですが、師匠はお見事でした。
仲入り後は「船徳」。
こちらも仕草が肝の一席です。
演じても多く、音声でも映像でも多くの落語家の「船徳」をみていますが、
その中でも最高の部類に入るこちらも“素晴らしい船徳”でした。
花緑師匠の落語は5回ほど経験していますが、常に上手くなっています。
【いもたつLife】
立川談笑独演会
久しぶりの談笑師匠でしたが、大満足です。
仲入り前に3演目、
「俳句入門」「代書屋」「原発息子」
独演会でなければ、けっして掛けない演目ありです。
最後の「富久」も見事な出来でした。
【いもたつLife】
立川志らく独演会 with ZAZEN BOYS
ZAZEN BOYSの出囃子で志らく師匠が登場。
「片棒」で仲入り。
ZAZEN BOYSの色物のあと、「紺屋高尾」でした。
「片棒」は志らく師匠の得意技を披露、師匠ならではの世界を作り出していました。
ZAZEN BOYSのファンの方々も多くいらっしゃり、雰囲気はいつもの落語会とは違う感じ。
しかし、「紺屋高尾」が始まると空気が落語になります。
アンコール演奏もありました。
志らく師匠30周年ファイナルということで、趣向を凝らした落語会でした。
【いもたつLife】
【SPAC演劇】舞台は夢 フレデリック・フィスバック演出

主人公のクランドールは、誰が見ても己が望んだ生き方でした。愛に忠実といえば聞こえは良いですが、愛の他には何も見えない生き方です。
では、それにつられる他の人物はどうかと言うと、彼を追う3人の女性も、彼の父プリダマンも、彼に振り回されながらも、実は彼と同じく己が望む生き方であって、人は自分のやりたいことは自分ではわからないものということでしょう。
プリダマンに厳しい躾を強いられることから家を飛び出したクランドール、10年経っても消息がつかめないことから、プリダマンは魔術師のアルカンドルにわが子を探して欲しいと訪ねます。
アルカンドルは今のクランドールが生きる実際を洞窟の中でプリダマンに見せる力がありました。するとクランドールは、マタモールというほら吹き隊長に仕える身でした。
マタモールは愛するイザベルに想いを告げるために、クランドールに託しイザベルの下に送り出します。
しかし、クランドールとイザベルは愛し合ってしまいます。イザベルにはアドラスト男爵との結婚が決まっていました。それを反故にするイザベル、当然諍いが起こります。
クランドールは過ってアドラストを殺めてしまい、牢獄へ、死刑判決です。
クランドールの運命は絶望的ですが、その時にイザベルの侍女のリーズの機転で、牢番を味方につけて、クランドールは牢獄から脱出です。イザベルとリーズと牢番の4人で生きる仕切り直しです。
数年後、領主に仕えるクランドールとイザベル夫婦、しかしクランドールは領主の妻のロジーヌと愛し合う関係になってしまいます。
それに勘付いた領主は、クランドールとロジーヌを亡き者にすることにします。それが決行されました。嘆くイザベルとリーズ、そしてそれらの一部始終をアルカンドルの力で俯瞰していたプリダマンも絶望します。
ところが実はクランドール達は生きていた。なぜなら・・・。
アルカンドルとプリダマンが俯瞰しながら、クランドールを中心に演劇が進みます。
基本的には悲劇ですが、狂言回しのマタモールがいることで、喜劇っぽくなります。最期のどんでん返しも悲劇を覆します。
マタモールは筋金入りのほら吹きです。出任せ以外は口から出てこない、しかも大法螺吹きです。誰も相手にされません。仕えているからばかりクランドールは従います。
しかし憎めない。なぜなら、彼は私の中にも居るからです。
彼は心の奥底には自分がほら吹きだという自覚がありますが、今ここに居る時の自分、ほらを吹いている自分は、しゃべっているその強がっている人物そのものになりきっています。また、そうでなければ今を生きられないのです。喜劇を演じる悲劇の人物です。
彼以外もそんな人達の人間模様です。
イザベルはクランドールを愛し続けます。アドラストと結婚した方が裕福で幸せになれますし、愛する父親を棄ててまでクランドールを取りました。最期にはクランドールに裏切られますが、ロジーヌとの仲を引き裂くことも結局はしません。領主の妻を奪うことで仕打ちを受けるクランドールの身を案ずるほどです。そして、クランドールがロジーヌを本当に愛していることを知ると彼を許そうとします。また、クランドールが死ぬと後を追おうともします。
イザベルは彼に献身したのに、裏切られる仕打ちを、その怒りを彼にぶつけますが、彼女もそんなクランドールを愛したことは己が望んだことだと気付きます。
この構図はリーズも同じです。
リーズはクランドールを牢獄から助け出すのですが、それには逡巡がありました。彼女もクランドールを愛していたからです。またクランドールもイザベルを愛しながらもリーズを愛していて、彼に、妻はイザベル、リーズは愛人として愛するとまで言われていました。
けれど、リーズはクランドールを助けます。
しかも、牢番を彼女の虜にしてという方法をとります。その代償は牢番と結婚することになるのですが、それをも受け入れます。それほどクランドールを愛したのです。
リーズもまともではないのではないかと思えますが、彼女も生きたい生き方をしました。
プリダマンも同じです。クランドールのためを思って厳しく躾ましたが、行方知れずになり、心配でしかたがありません。アルカンドルを頼るのは、もちろんクランドールのことが心配だからですが、自分の心が探さずにはいられないのです。
もうクランドールは彼が生きたい人生を歩んでいます。でもプリダマンは息子の心配をする生き方がプリダマンの生き方なのです。
クランドールが死刑になる時も、領主の手に落ちた時も絶望します。親として当然ですが、どこまでも息子を追う姿は自律した姿ではありません。でもそれがプリダマンの生き様です。
クランドールは、お世辞にも褒められたものではありません。同時に何人もの女性を愛するのですから。しかも、その行為に悪びれたところが全くありません。自己に忠実なのです。
あまりにも自分を飾る生き方を身につけてしまっている私達に異を唱えているかのようです。原作ができた17世紀のフランスは、自分の愛に忠実なのが当然だったのか、その時代も社会に取り込まれて自己を隠してしまう風情だったのか、ただ、どちらも人が持つ普遍的なものだということでしょう。
この演劇は、アルカンドルとプリダマンが俯瞰するという構図で繰り広げられます。その時点で観客は俯瞰視点になります。しかも、プリダマンがクランドール達を見ている姿が舞台上の大きなスリーンに映るのです。だから劇中の人物に想いを入れながら少し冷静になります。それが最後のどんでん返しにも活きてくるという構造は見事です。
そして演出もそれを考慮に入れられています。
面白い演出として、先ほどのプリダマン達を撮るカメラが場面によってはクランドール達を捉えながら劇が進むことです。役者の顔のアップが大きなスクリーンに映し出されます。そしてもちろん観客は演じる役者そのものと、大きなスクリーンの姿と両方を観ることになります。
この演出は主に登場人物の内面を吐露するところと、ラストのクライマックスのクランドールとロジーヌの密会のシーン、ここでクランドールとイザベルのこれまでの愛と各々の愛についての語らいと、同じくクランドールとロジーヌの愛の語らいで使われます。
観る者は登場人物の内面の痛みをひしひしと感じる演出です。
演劇後のアフタートークでも話されていましたが、役者さんたちは、かなりカメラを意識するようです。マイクも口元にまできて、普段の舞台上の体一杯、声一杯に使った表現とは別の演技とのことです。
登場人物の内面を静かな声で、でも我々にはマイクを通した大きな音量になることで、その場面の揺れる心理がより伝わり、そして大きな気持ちの揺れであることが伝わってくる演出だと思いました。
また同じくアフタートークで、演出家のフレデリック・フィスバック氏から、自分の心の内面を素直に出す、自分に嘘を付かないでの演技を求められたとのことです。
なるほど、この演劇のテーマの、自己が求めている生き方を見つめるに沿っているし、人との関係で進むこの劇には適切な演出になるのだと納得しました。
喜劇を帯びた悲劇で最後はほっとする、楽しめる劇を、シンプルな舞台ででもスリリングな演出になっていたspacの「舞台は夢」、堪能しました。
追伸
10/2に、10月の「毎月お届け干し芋」出荷しました。
今月のお宝ほしいもは、“有機紅あずま平ほしいも”です。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
毎月お届けの「今月のお宝ほしいも」の直接ページはこちら
今月のお宝ほしいも
【いもたつLife】
舞台は夢 コルネイユ作 井村純一訳

SPACの「舞台は夢」の観劇があるので、原作を抑えようと読みました。
面白い戯曲でした。演劇が楽しみになった反面、読んでない方がドンデン返しを楽しめたかもという効果も少し。
色々な演出で上演されている訳がわかる痛快な話です。
落語に出てくるような人物がいたりしますが、私は落語の登場人物は、ちょっと強調された普通の人だと思っていますので、この話の人物も、決して誉められない輩が多いですが、自分と重ねてしまいます。
それよりも、入れ子構造になっている点と、魔術師を登場させて主人公の父親が息子のことを心配し、魔術師に息子の動向を見せてもらうという構造が、戯曲全体の俯瞰になっていて、登場人物一人ひとりを注視できるところが優れています。
そして最後がまた痛快です。
SPACの「舞台は夢」はどんな仕上がりか、観劇が待ち遠しくなりました。
【いもたつLife】
ビジネスパーソンのための易経入門 岡本史郎 著

易経をかじっています。
この本は易の入門書でもあり、易を説くためのヒントが散りばめられているので、
易の世界観が変わるごとに読むと、易との新しい付き合い方を見つけられそうです。
それだけ、易に対しての多面的な捉え方を著者がしているからでしょう。
そして、易の出自や本質を説明し、それと共に実践例と絡めて、
易を実務で役立たせることを目的にしています。
また何より素晴らしいのは、哲学である易経を、
身近な指南書たる存在であることを知らしめてくれていることです。
易をかじっている私の今の時点での易との付き合いで、
その効用を得る嗜みを教授していただきました。
【いもたつLife】